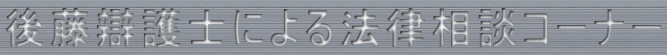
| かけはし誌上コラム(かけはし掲載分) | 羽田鉄工団地協同組合 |
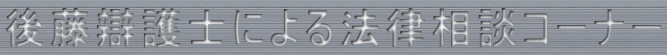
| 最新号(平成25年12月) | |
| 平成25年 1月 | 「役に立つ労働法の知識②」 |
| 2月 | 「役に立つ労働法の知識③」 |
| 3月 | 「役に立つ労働法の知識④」 |
| 4月 | 「役に立つ労働法の知識⑤」 |
| 5月 | 「役に立つ労働法の知識⑥」 |
| 6月 | 「役に立つ労働法の知識⑦」 |
| 7月 | 「役に立つ労働法の知識⑧」 |
| 8月 | 「役に立つ労働法の知識⑨」 |
| 9月 | 「裁判あれこれーその証言、信用できるか」 |
| 10月 | 「裁判あれこれー書証の偽造」 |
| 11月 | 「裁判あれこれ~尋問の醍醐味~」 |
| 12月 | 「経営者としての心構えと配慮義務について」 |
平成25年12月
「経営者としての心構えと配慮義務について」
1 経営者は、会社を永続させなければならない。会社50年と言われるが、100年以上も続く企業にするために。
会社を潰さないことが経営者の仕事であるということを常に考えていなければならない。
生き残り競争に打ち勝ち、永続するためには、「変わらないためには、変わらなければならない。」のであり、そのためには、事業や商品(製品)を常に時代に適合したものに変えていく必要がある。それを支えるのは、従業員である。経営者はそのことを忘れてはならない。
そこに経営者としての配慮義務が課される。
2 会社が潰れる原因を考える。ひとつは商道徳違反である。船場吉兆は違法行為によって潰れたのではなく、料理の使い回しをし、発覚したことが顧客の信用を失い、潰れることになったことは象徴的である。最近では、食材の虚偽表示(不当景品類及び不当表示防止法4条1項「優良誤認」違反。ただし、優良誤認の行為をしたこと自体には罰則はないが、行政庁がこれに対する当該行為の差し止めなどを命じたのにこれに従わなかったときは個人には2年以下の懲役又は300万円以下の罰金、事業者には3億円以下の罰金がある。)の例やみずほ銀行の反社会的勢力との取引とその放置の例などがある。
これらの事例は、
ア 法律(ルール)がなければ何んでもやってよいか。
イ バレなければ何をしてもよいか。
ウ 自社だけが儲かればよいのか。儲かるためには何をしてもよいか。
という問題を提起している。
3 やっていいことと、やってはいけないことの判断力を備えなければならないが、経営者は、いかにしてそれを養うかが極めて大切だということになる。
会社の良識とは?正々堂々の精神とは?世間における会社の信用とは?を常に考えていなければならない。
ルールがあろうがなかろうが,誰が見ていようがいまいが、会社として、後ろ指を指されるようなことがないほどのちゃんとした仕事をするという気構えがあるかどうかが問われる。
4 経営者が経営方針をきっちりと立てたうえで、あとはこれを支える従業員をいかに育て、活用するかということになる。経営者が経営者として本領を発揮するところである。
会社を支えるのが従業員であるという認識を持っていれば、単なる人材に留まらず、人財となる。
そのような従業員を人として大切にし、その人格を尊重することは当然のことである。これに反するのがハラスメント(パワーハラスメントとセクシュアルハラスメントがある。)である。あるいはブラック企業といわれる労働法規等の無視を平気で行う企業である。
人を人として大切にする会社には、ハラスメントは起きるはずがない。従業員の個人としての尊厳と人格を尊重する会社には、ハラスメントが起きるはずがないのである。これらを無視したり、軽視したときに起きるのであるから、経営者としては、管理職を含む従業員に対する啓発啓蒙を行う配慮義務が課される。
せっかくの人材(財)を途中で失い、損失を被るということもないはずである。
そのためには、人事管理もそのような配慮に基づくものでなければならない。
人事管理の要諦は、①戦略的人事、②十分な教育・指導、③毅然たる措置の3つであると考えられる。
場当たり的な採用ではなく、会社の方針に基づく戦略的な採用計画、労基法等の関連労働法を遵守した規律ある雇用契約が必要であり、一旦採用した従業員には十分な教育・指導を尽くし、育てる必要がある。そして、せっかく育てた従業員には、会社の歴史、伝統、文化、ノウハウといったものが染みついてるのであるから、これを活かさない手はない。しかし、それでも問題を起こす従業員がいれば、最後は毅然たる措置を講じるのが会社としての当然執るべき態度ということになる。こうすれば、秩序が保たれ、社内にも緊張感が出てくる。
目指す会社は、①募集力のある会社すなわち来て欲しい人を採用できる会社、②教育力のある会社すなわち採用した従業員には徹底的に教育できる会社、③定着力のある会社すなわち途中退社によってそれまで投下した時間と費用が無駄にならないように、居て欲しい従業員には定着して貰える会社である。
5 もうひとつ、経営者として忘れてならないことがある。労働組合の問題である。労働組合を徹底的に嫌う経営者がいる。しかし、もし労働組合ができたのであれば、何故、組織されるようになったのかを考えてみなければならない。あるいは個人で加入できる合同労組に加入した従業員が出てきた場合も同様である。
労働組合に対して、無用の先入観を持つ必要はない。労働組合というものはどういうものなのかを知らず、労働組合との付き合いが分からないと根拠なくおそれたり、過剰反応を起こしたりして、結局、会社としての労働組合に対する取り組みを間違え、信用を失うこともある。ついには、経営者は労働組合との対応に疲れて、事業譲渡(仮装譲渡)や解散、清算してしまうということがある。自分の作った会社だから、止める自由があるという考えからである。しかし、それは身勝手かつ無責任な態度であり、絶対あってはならないことである。従業員のことを考えていない暴挙ともいうべきものであろう。
したがって、経営者は、労働組合法を含む労働法規及び労働組合についても正しい知識を持たなければならない。企業別組合が日本の労働組合の特徴であったが、今や、ひとり加入のできる合同労組が増えている。労働委員会が扱う労働事件の6割から7割は、合同労組の事件であることからすると、会社に労働組合がないからといって、従業員が労働組合に加入することや労働組合に対する対処の仕方を考えなくともよいということにはならないだろう。
平成25年11月
「裁判あれこれ~尋問の醍醐味~」
1 本号は、前号に続き、「裁判あれこれ」シリーズの3回目として「尋問の醍醐味」の話を致します。
裁判は、真相(真実)を明らかにするところですが、真相の発見(何が真実か)を巡って、もっとも白熱するのが証人尋問という場面です。証人尋問は、質問者と答える側とのやりとりの中で、真相を明らかにしていくものですから、なかなか難しく、苦労は尽きないというところがあります。尋問の行われる当日は当然の如く緊張感がありますし、今は集中審理といって、事件によっては、朝から夕方までぶっ通しで証人尋問が行われますから、大分疲れます。健康で体力がなければ到底務まりません。しかも良心的な弁護士なら、前夜になっても「明日は大丈夫か、見落としはないか」などと考えているうちに、つい明け方まで、記録を読み返すということになるのが通例と思います。手間暇をいかにかけたかで勝負はつくなどと言われますので、相当の時間をかけ、しかも、真摯に一生懸命に証人尋問の準備をします。それだからこそでしょうか。証人尋問が無事終了したときの達成感、納得感はこれにまさるものはありません。特に、想定どおりの尋問ができ、真相を明らかにし、裁判官にも十分な説得ができ、納得をしてもらうことができたと考えられるときは弁護士冥利につきるものです。これは苦労したことに対するご褒美ということでしょう。
2 証人尋問における質問は、できるだけ、個別的かつ具体的にしなければなりません。証人を侮辱したり、困惑させるよ うな質問はしてはなりません。誘導質問(質問に答えが入っている質問)、誤導質問(真実かどうか確定していない事実を真実という前提でする質問)、重複質問、争点と関連性のない質問、意見の陳述を求める質問、証人が直接経験していない事実についての陳述を求める質問は、原則として許されません。
もし、このような質問が自らの証人にされた場合は、弁護士としては、看過することはできません。真実発見を誤るおそれがあるうえ、証人を守る必要もあるからです。適切に異議を述べて、その質問をストップさせなければなりません。相手方の証人に対しては、反対尋問をすることとなります。反対尋問の目的は、相手方の証人の証言の信憑性を弾劾することにあります。抽象的な部分、具体性のない部分、憶測、推測、意見的な部分についての信用性を潰していきます。ところが、弁護士の習性でしょうか。自己に有利な証言を引きだそうとして、深入りしてしまうことも多く、それで失敗に終わることもあるものです。
3 では、反対尋問で深入りしてしまい、失敗した有名な例を紹介します。ストライカーの「耳噛み切り事件」というものです。被告人が被害者の耳を噛み切ったという傷害罪で起訴された事件について、検察官の主尋問で、その証人は、「喧嘩をしているのを見たが、問題となっている被告人が被害者の耳を噛み切ったという出来事は見ていない。」と証言しました。被告人の弁護人は、気負って反対尋問に立ち上がり、「そこでだ、君。君は、わしの依頼者が被害者の耳を噛み切るところは見ていないと証言したわけだね。」と質問したところ、証人は、重ねてそれを認めた。したがって、弁護人は、ここで止めておけば良かったのであるが、さらに次のように深入りしてしまった例です。
弁護人 「では君が実際に見たのは何かね。」
証 人 「そうですね。道をこう歩いてきたんですよ。私はちょうど、その時、あの人が口か ら被害者の耳を吐き出すところを見たんですわ。」
これで反対尋問は台無しとなり、被告人は有罪となってしまったという実例です。
反対尋問の教訓として、いつ尋問を打ち切るべきかを学ばなければならない、と言われます。直撃弾を放つことに成功したら、他のことは一切忘れて着席することである、ということです。「百合の花を金箔で塗り立てるようなことをしてはならない。最後の致命的な一問を試みることによって折角の成果を台無しにしてはならない。」(古賀正義・弁護の技術 日本評論社98頁参照)
法廷の場では、なかなか難しいのですが、冷静さを失ってはならないということですね。
4 ここで、エイブラハム・リンカーン(アメリカの第16代大統領)の若き弁護士時代の有名な反対尋問の実例を紹介して本号を閉めたいと思います。「ムーンライト・クエスチョン」(日本弁護士連合会編「法廷弁護技術・第2版184頁 日本評論社2009年参照)
ある年の8月9日夜、ある教派の野外集会で、拳銃で射殺されたという殺人事件につき、検察官は、被告人を殺人行為を行った犯人とし、その一部始終を目撃したというA証人にその旨の証言をさせました。法廷の誰もが被告人を犯人と疑わざるを得なかった。これに対し、リンカーンは、その他の証人には一切反対尋問をせず、このA証人には次のように、反対尋問をしました。
リ Aさん、あなたは被告人と犯行直前まで一緒にいて、被告人が狙撃するのを見たというのですね。
A はい。
リ 被告人のすぐ近くに立っていたということになりますね。
A いえ、6メートルほど離れていました。
リ 3メートル位じゃなかったですか。
A いいえ、6メートルかそれ以上です。
リ 犯行時刻は、何時ころですか。
A 夜10時ころでした。
リ そこは広い野原でしたか。
A いや、林の中でした。
リ 何の林でしたか。
A ブナの林です。
リ 8月といえば、木の葉がかなり繁っていますね。
A どちらかといえばそうですね。
リ あなたは被告人が狙撃するところを見ましたか。
A はい。
リ 銃身をどんなふうにぶら下げていたとか、そんなところが全部見えましたか。
A はい。
リ 現場は、集会場からどのくらい離れていましたか。
A 1.2キロメートルほどです。
リ 電灯はついていましたか。
A 集会場の牧師席の脇についていました。
リ 1.2キロメートルも離れたところに電灯があっただけですね。
A はい。
リ あなたや被告人はろうそくでも持っていましたか。
A いいえ。どうしてそんなものを持っていなければならないのですか。
リ では、どうして、あなたは、被告人が狙撃する様子をみることができたのですか。
A 月明かりですよ。
リ 電灯は1.2キロメートルも離れたところにあった。あなたは被告人から6メートルも離れていた。明かりは月明かりのみ。夜の10時。それですべてが見えたということですか。
A はい。何度も申しています。
リンカーンは、上着のポケットから青い表紙の暦を取り出し、問題の夜の月齢表のある 頁を開き、証人の前に置いた。
リ この暦によれば、8月9日は、月は見えず、翌10日午前1時にならないと昇らないという ことになっていますね。
言いたいことを言わせ、外堀を固めておいてから、客観的な証拠(月明かりがなく目撃できる余地がないこと)を示すことで反対尋問を成功させた例です。
平成25年10月
「裁判あれこれー書証の偽造」
1 本号は、前号の続きとして「裁判あれこれ」シリーズの「書証という証拠の偽造」の話です。
前号は、いわば証言の虚偽に絡む話でしたが、本号は、文書という証拠(これを書証と言います。)の偽造に絡む話です。
前号の甲の乙に対する100万円を貸したケースを例として取り上げます。
甲は、A弁護士から、「客観的な証拠は何もないのか」と詰問され、「借用書がないととても勝ち目がない」とも言われ、困った甲が、乙名義の借用書を作ってしまったという場合です。
法治国家のもとで、このようなことがあってはならないのですが、甲にしてみれば、確かに、乙に100万円を貸したのであり、それは事実であるという思いがあります。それなのに、乙の「借りた覚えはない、借りたことはないのであるから、返す義務などない」という態度が許せません。そこで憤慨した甲が、客観的事実に合致するのだからという理由で、後先も考えずに乙作成名義の借用書を偽造してしまったというものです。
ここで、強調しておきたいことは、いくら事実に沿うからといって、他人名義の借用書などを勝手に作成することはあってはならないということです。これは文書偽造という立派な刑法犯(刑法159条)になります。
2 世の中には、こんなだいそれたことをする人がいるのかと訝る方もいるものと思います。けっして一般的な例ではないのですが、それでも書証の偽造が問題になる例が実際にはあるのです。
民事裁判の当事者は、「信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。」(民事訴訟法2条)のであり、裁判は真実を発見する場であり、証拠裁判ですから、その基となる裁判に提出されるべき証拠は、偽証であったり、偽造文書であったりしてはならないはずです。
3 甲は、本件より20年も前に、乙に10万円を貸したことがあったことを思い出し、その時の借用書がたまたま手元に残っていたこと、そのうえ乙に100万円を貸したことは間違いない事実でもあることから、昭和58年10月1日付けの10万円の借用書に手を加えて、平成15年10月1日に100万円を貸したとする乙名義の借用書を作成したということになります。
手口は、こうです。甲は、まず10万円の借用書のコピーを取り、昭和を消し、その上に平成と書き、58年の5の前に1を加えて、8を消し、平成15年とし、10万円の0のあとに0を付け加えて100万円とし、乙の署名と押印は、10万円のときのものをそのまま使った、というものです。それを書き加えたことが不鮮明になるまで、なんどかコピーを繰り返しました。
A弁護士は、訴状を作成したうえ、甲がFAXで送信した書面を甲第1号証としました。A弁護士は、後日、甲から原本を受領できるものと信頼したことはいうまでもありません。A弁護士にしてみれば、依頼者が借用書を偽造するなどということは到底想定し得ないことです。
4 訴訟を提起すれば、訴状副本と証拠の写しが被告にも送達されます。乙は、平成15年10月1日付けの100万円の借用書を書いた事実はなかったので、どうして自分の署名・しかも実印の押してある借用書があるのか、不思議でなりませんでした。借用書には印紙も貼ってあります。この200円の印紙には、割り印まで押してあります。
5 乙から被告訴訟代理人として受任したB弁護士は、乙と打ち合わせをしたうえ、次のような内容の答弁書を作成しました。
乙が甲から平成15年10月1日、100万円を借りた事実は否認する。甲第1号証中の乙の署名及び押印は認めるが、この100万円の借用書を乙が作成したことは否認する。甲の乙に対する本件請求は棄却する、との判決を求める。
裁判の第1回期日まで、乙側は、甲第1号証の原本を確認することはできません。乙とB弁護士との答弁書作成のための打ち合わせでは、甲第1号証の借用書は、100万円の借用書なのに、貼付されているのは200円の印紙であることは不自然であること(100万円なら1000円の額の印紙でなければならない。)は容易に判明しました。しかし、それよりも乙にとって理解し難いことは、乙の署名と乙の実印による押印です。
乙としては、100万円を借りた際に借用書を作成したことはありませんので、このような借用書が存在することが信じられなかったのです。確かに、送達された甲第1号証を子細に検討すると、「100万円」の「10」と次の「0」との間がくっついていることも不自然ではありました。
6 民事訴訟法228条4項は、「私文書は、本人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」と規定していますから、裁判実務では、私文書である借用書の甲第1号証は、乙が作成したものと推定され、その結果、この甲第1号証に記載されているとおり、乙は、甲から平成15年10月1日、100万円を借り受けたという事実が認められると認定するのが、一般です。
したがって、乙としては、甲第1号証が真正に成立したことの推定を覆す立証をしなければなりません。これに成功しなければ、甲第1号証の存在から、乙は敗訴してしまうこととなります。乙が甲から真実100万円を借りているなら、それもやむを得ないということにはなりますが。
7 民事裁判では、書証の偽造(後日作成の事実)が見破られた例として、次のような例があります。
① 昭和の時代に作ったはずの書面に平成の文字の記載が入っている例。
② 消費税の税率が3パーセントの時期に作成された領収書に5パーセントで計算された額が記載されている例。
③ 貼付されるべき額の印紙額が作成年度のそれと違っている例。
④ 郵便番号や電話番号の桁数が増加する前の作成文書であるのに変更後の番号が記載されている例。
⑤ 用紙の製造が作成当時にはまだ製造されていなかったと判明した例。
⑥ 書証の文字がワープロやパソコンで打たれたものであるとき、その当時の品位としては不自然に高精細であることが判明した例。
⑦ 既存の書面を切り貼りして作成しそれをコピーしたことが判明した例。
8 これらの例は、書証は、すべからく原本を確認することが必要かつ重要であることを示唆しています。コピーでは、数字が書き換えられたり、切り貼りされて作成されたことを見破ることは困難な場合がありますが、原本を確認することでこれらを容易に発見することができます。
平成25年9月
「裁判あれこれーその証言、信用できるか」
1 暫く、堅苦しい法律の話が続きましたので、本号では、少し息抜きをしたいと思います。肩のこらない内容としましたので、気楽に読んでください。
2 裁判は、真実を発見する場であると言われます。裁判をすれば、真実あるいは真相がはっきりす る、明らかにされる、と考えられています。確かに、そうであり、弁護士を生業とする私も、期待も込 めて、そのように考えています。法廷での証言をもって真実を明らかにできた場合は劇的でもあり、大きな達成感を得られます。
3 「裁判における真実」とは何か。
裁判で提出された証拠に基づき、裁判官が経験則と論理則とによって、その証拠を合理的に評価した結果に基づいて認定判断される事実が「裁判における真実」です。あるいは「裁判上の真実」と言われるものです。裁判官は、この事実に法を適用して結論を出すわけです。
裁判は、「証拠裁判」とも言われますように、裁判は、証拠によって結論が左右されます。どのような証拠をいかに効果的に提出するかが極めて大事だということになります。代理人となる弁護士がどのように証拠を収集して、これらをいかに効果的に提出するか、そして相手の証拠をどのように崩すかが勝訴の決め手になると言っても過言ではありません。虚偽を述べる相手方に対しては効果的な反対尋問を行ってその虚偽を明らかにします。
4 次のような事例がありました。
A弁護士は、長い付き合いのある甲から次のような相談を受けました。
「甲は、かねてより親しい付き合いをしている友人乙に対し、平成22年10月1日に100万円を貸した。乙は3年にもなろうとしているのに、返さない。毎年のように催告してきたが、今回は妻が病床にあることもあり、強く返済を迫ったところ、乙は借りた覚えはない、などと返済しようとしないどころか、借りたことすら否定した。甲によれば、確実に100万円は貸したということなので、乙の不義理と豹変が許せない。そこで、先生、裁判して返して貰ってください。」
という提訴の依頼だった。
A弁護士は、更に甲に対し、裏付けとなるべき証拠について注意深く確認したうえ、甲の貸し付けるに至った経緯や乙の借り受けの動機、目的などについて、当時乙からどのように説明されていたかなどの事情も聴取した。
甲は、これに対して次のように答えた。
「当時乙とは親しい友人だったし、乙が細かい借金の返済に困っているという話だったので、100万円を貸すこととした。しかし、100万円を貸すに当たっては、借用書を作成するのは大人げないと考えたので、作成しなかった。100万円は、タンスにしまって貯めていたものを現金で乙に手渡した。その時立ち会った人はいなかった。それまでも借用書など作らず、小口で貸したことはあったが、返済はして貰っていた。」と。
5 借用書もなく、立会人もなく、貸金を相手の口座に振り込んだ証拠もないのに、弁護士は依頼を受ければ、裁判まで提起するのですか、という質問を受けそうです。弁護士とて、証拠が整っている事案であれば、闘い安いのは当然であり、それがないという場合は、勝ち抜くことは困難と考え、場合によっては、受任を拒否することもあります。合理的な証拠もなく訴えれば、不当訴訟として逆に訴えられることも覚悟しなければならないからです。
A弁護士は、甲からのたっての依頼なので、裁判を提起することとしました。このような事件でも裁判所は受理するものであるし、裁判は、淡々と進み、双方の主張と証拠整理(争点整理)を経て、結局、甲(原告)と乙(被告)双方本人尋問以外に有力な証拠は考えられないとして、双方の本人尋問が実施されることとなりました。
6 借用書等有力な客観的証拠がなく、相手が激しく争っている場合でも、真実、貸し付けたなら、「正義必勝」、勝つべき者は勝たなければならないのであるから、甲は勝訴できなければならない。
A弁護士は、双方の本人尋問の結果によって、担当裁判官に貸し付けたという心証を抱かせなければならないこととなります。
7 尋問では、甲は、A弁護士の質問(主尋問)に答えて、乙に100万円を貸したと述べ、乙は、その代理人B弁護士の質問(主尋問)に答えて、甲からそのようなお金を借りた事実はない、と述べたほかは、概ねA弁護士が甲から聴取した事実が立証されました。そして、甲の主尋問の結果は、B弁護士の反対尋問でも揺らぐことはありませんでした。
残るは、A弁護士の乙に対する反対尋問で、乙が嘘を言っており、甲の述べていることが真実であるとの心証を裁判官に抱かせることとなります。
皆さんならどのような質問によって、乙の述べていることが嘘であり、甲の言っていることが真実であるとの心証を裁判官に抱かせることができると思いますか。
A弁護士は、本件の「動かし難い事実」と言われる事実に注目しました。この「動かし難い事実」に乙の供述が反する場合は、信用性はないと判断されるし、相対的に、甲の言い分が信用性を持つに至ると考えられるからです。
A弁護士は、乙に対して、きめ細かく反対尋問をして、「動かし難い事実」に反する内容を引き出すこととし、この「動かし難い事実」は、次の3つの段階に分けると分かりやすいだろうと考えて質問し、そのうえで、以下のような事実を引き出しました。
① 「貸し付けるまでの事情」
甲と乙とは、親しい関係にあること(甲が乙に頼まれればお金を貸すことがあっても不自然ではないこと、その関係からすれば借用書を作成しなかったことも非常識とはいえないことが窺われます。)、本件貸し付け前にも乙は甲から借りた事実があること、その時も借用書は作成されていないが、乙はきちんと返済した事実があること(このような過去の例があるとすれば、今回の貸し付けもないとは言えないと窺われるし、借用書がないという一事では貸付を否定はできなくなる。)
② 「貸し付けた際の事情」
当時、乙は、複数の借金があったこと、そしてこれらを返済した事実があること、乙の預金口座からその借金の返済資金が引き出された事実はないこと(これらからすれば、乙は甲から借りたお金で借金を返済したものと窺われる。)。
③ 「貸した後の事情」
甲から乙が過去2年間、毎年9月ころに100万円の返済を催促されたことがあること、その際、乙は、借りていないとは言っていなかったこと(返済催告の事実は、甲の貸し付けの事実を推認させ、乙が「借りた事実はない」と言っていないこともこれに沿うものと言える。このように乙の対応が「待ってくれ」と言ったのか、「何をとぼけたことを言っているのだ、借りた覚えはない」などと言っていたのかによっても心証は違ってくる。)。
8 証拠が不足していて、万事休す、のように見える事件でも、有能な弁護士の周到な準備と尋問技術により、「正義必勝」の実現を果たすことができるのです。
通り一遍の尋問をするだけでは到底勝訴は覚束ないが、この例のようにきめ細かい尋問をすることで、嘘を述べる不正義者を負かすことは可能となるのです。
日本の訴訟法は、借用書がないと貸し付けの事実を証明できない、という証拠法則ではありません。したがって、このような立証方法によって勝訴を勝ち獲ることができることを忘れてはなりません。
平成25年8月
「改正高年齢者雇用安定法について~役に立つ労働法の知識⑨~」
本号は、前回に続く改正高年齢者雇用安定法についての説明です。
1 再雇用する場合、雇用態様としては、正規社員として雇用することまで義務付けたものではないので、1年毎の有期雇 用契約でもよいし、常勤でなくともよい、について
(1) 嘱託のような契約態様でもよく、1年毎の契約でもよい、ということであり勤務も毎日のように常勤ではなくともよいとされています。
(2) そうすると、働きに応じた賃金体系が適用されることとなりますので、賃金面の待遇は、定年前のものと違って、悪くなることは否めません。
例えば、賃金が定年前の3分の1程度になることがあってもやむを得ない、ということになります。
大幅に再雇用時の賃金が低下しても、公序良俗違反や不当差別とはいえません(大阪高裁平成22年9月14日判決 労契速2091・7)。
(3) もっとも、定年前の仕事と全く同じであれば、労働契約法20条の問題になる場合があります。すなわち、有期雇用契約であるが故の不合理な労働条件として無効となる場合がありますので、注意を要します。
(4) 一般的には、定年前とは異なる勤務態様でしょうから、実際上の問題はないものと考えられます。
2 これまでは、問題のある社員(辞めて貰いたいと考えている社員)であっても、定年まで待てば雇用関係が終了するのだ から、定年を迎えるまでは、そっとしておこうという対応をしていたが、今後5年間雇用を継続しなければならないとすれば 、これまでと同様に雇用を継続してよいか、について
(1) これを避けるためには、就業規則上の解雇規定をきちんと適用せざるを得ない場合があるということです。これからは「60歳だから辞めろ」ではなく、「能力がないから辞めろ」ということになるのではないかと思います。
60歳の定年前にも辞めて頂くことが出てもやむを得ないということです。
ある意味では、「年齢に関わりなく働ける」から「年齢に関わりなくクビになる」という時代を迎えているのではないかということです。
(2) 再雇用する際(更新する場合)の基準を設定しておく必要がある、ということになります。
そうでないと、60歳まで雇えたのであるから、何故、65歳まで雇えないのか、ということを問題にされ、ずるずると雇用を継続しなければならないことにもなりかねません。
① 定年は必ず定める。例えば、65歳とする。
② 再雇用基準を定める。解雇・退職規定は必ず定める。退職・解雇事由があったり、懲戒処分該当事由があれば、必ずしも雇用を継続しなければならないというものではありません。
(3) もし、単に、定年後も再雇用する、と規定していると、労働者には雇用請求権が発生することに注意です。
就業規則で再雇用基準・賃金等も定めているなら、該当者を私法上再雇用する義務があります。労契法7条により、当該就業規則は労働契約の内容となるからです。
使用者がこのような場合に再雇用を拒絶することは雇い止めとなり、解雇権濫用法理が類推適用されます(最高裁平成24年11月29日判決津田電気計器事件)。
(4) 60歳以上の再雇用が原則となれば、再雇用制度の内容にもよりますが、40代、50代から賃金カーブの上昇を抑制するようなことも考えなければならないということになります。
3 高年齢者雇用安定法により、企業は、60歳を超えた社員のうち希望者は全員雇用する義務が発生するが、当該企業 が、業績悪化により、その余裕がないときは雇用することが義務付けられないか、について
(1) 企業が倒産等の危機に瀕している状態のときにも、高年齢法に従い、高年齢者を雇用しなければならないものと解されません。企業あっての雇用ですから、当然です。高年齢者を雇用することで、企業が倒産しては元も子もありません。
(2) 企業が社員を整理解雇しなければならないような業績の悪化が見られるときに、高年齢者を雇用せず、あるいは高年齢者から人員整理することはあり得ます。
4 再雇用希望者を再雇用しなかったときには、当然に再雇用したとみなされることはない、について
(1) 本来は、制度として、再雇用制度を導入することを会社に義務付けているだけで、個々の社員を雇用することまで義務付けたものではありません。私法上の雇用請求権を直接発生させるものではなく、あくまでも制度導入義務を課したものだからです。なお、このような制度は、行政上の国に対する義務(違反の場合に勧告、企業名の公表等の制裁がある。)であって、私法上の効力はないとされています。
(2) ただし、前記のように、企業において、就業規則で、定年後の再雇用を定めているときは、この規則の定めに従い、雇用する義務が生じますので、注意を要します。
(3) 仮に、1年毎に契約を更新していく契約である場合、解雇・退職に当たる事由がある場合は、更新を拒絶できるとすることが必要です。
この場合、労働契約法19条2号に該当するので、「更新することの期待を抱かせた」がどうかが問題となり、これが肯定される場合は、更新を拒絶するときには、解雇権濫用法理の類推適用を受けるということになります。
5 「特殊関係事業主」である子会社でも、再雇用できることとなったことから、定年後のA社員を埼玉にある子会社で再雇用して働かせようとしたところ、A社員は、病気がちの妻と二人暮らしであり、埼玉の子会社までは到底通えない、という場合にこの再雇用は何ら法的な問題はないのか、について
(1) 原則として問題はありません。
(2) ただし、東京近郊の職場があるのに、わざわざ埼玉にある子会社において再雇用することとした目的・動機等において問題がある場合、このような場合は配転と同じように考察して、通常甘受しなければならない限度を超えて不利益を与えるような場合には、権利の濫用の問題が出てくるおそれはあります。しかしだからと言って、労働者にもっと近いところで働かせろという請求権があるとは解されません。
平成25年7月
「高年齢者雇用安定法の改正について~役に立つ労働法の知識⑧~」
本号からは、平成25年4月1日から施行されている改正高年齢者雇用安定法についての説明を致します。各社におかれましては、社員の定年後の再雇用問題に頭を悩ませているかも知れませんので、取り上げてみました。
考えてみれば、3分の1が非正規社員で、3分の2は正規社員ですから、一般的には、前号までに取り上げてきた有期契約社員の問題よりも、切実な問題であるとも言えます。
1 平成25年4月1日施行された改正の最大のポイントは、再雇用希望者全員を65歳までは、雇用するよう企業に義務付けたということです。
2 改正前は、労使協定で、再雇用基準を設定できました。この基準をクリアしない場合は雇用しないことができました。これからはこのようなことはできないということになりました。
3 もっとも、雇用しなければならないといっても、雇用態様としては、正規社員として雇用することまで義務付けたものではないので、1年毎の期間契約でもよいし、常勤でなくともよいので、賃金等のコスト面を抑えることは可能です。
4 これまでは、問題のある社員(辞めて貰いたいと考えている社員)であっても、定年になれば雇用関係が終了するのだから、定年を迎えるまでは、そっとしておこうという対応をしていたと思われます。
しかし、今後もこれまでのような対応でよいのかという疑問が出てきます。
60歳まで雇えたのであるから、何故、65歳まで雇えないのか、ということを問題にされることが想定されます。
5 改正によるいろいろな問題を想定問答の形式として考えてみました。
(1)問 改正後は、就業規則上の定年の定めは無効となるのですか。
解答 いいえ、そうではありません。定年60歳の就業規則の定めをしていても無効となるものではありません。
改正法が規定していることは次のとおりです。
①定年の65歳までの引き上げ
②希望者全員対象の65歳までの雇用継続制度
③定年の廃止
ほとんどの会社は、②の制度を導入しています。この制度導入に際し、従前の60歳定年制を維持したままで可能だからです。
(2)問 改正後は、定年を65歳に改めなければならないのですか。
解答 いいえ、そうではありません。60歳のままにしていてもよいのですが、希望があれば、65歳まで雇用する義務があります、ということです。
(3)問 60歳定年に達した社員は、希望すれば全員再雇用しなければならないのですか。
解答 原則として、そのとおりです。ただし、解雇規定に当たるような事例であれば、再雇用しなくともよい場合があります。
企業において、高年齢者を継続雇用する制度があったとしても、常に、当該高年齢者を雇用しなければならないわけではありません。
退職・解雇事由があったり、懲戒処分該当事由があれば、必ずしも雇用を継続しなければならないというものではありません。
ア 健康上の理由で職務に耐えられないこと。
イ 解雇又は退職事由に該当すること。
ウ 懲戒処分該当事由に該当すること。
企業が整理解雇しなければならないような業績の悪化が見られるときに、高年齢者を雇用せず、あるいは高年齢者から人員整理することはあり得ます。
(4) 問 再雇用希望者を再雇用しなかった場合、会社は、罰則を受けるのですか。
解答 いいえ、そのような規定はありませんが、高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業は、その企業名を公表等されるということがあります。
(5) 問 再雇用希望者を再雇用しなかったとしても、当然に再雇用したとみなされるのですか。
解答 いいえ、そうではありません。制度として、再雇用制度を導入することを会社に義務づけているだけで、個々の社員を雇用することまで義務づけたものではありません。私法上の雇用請求権を直接発生させるものではなく、あくまでも制度導入義務を課したものだからです。
なお、このような制度は、行政上の国に対する義務(違反の場合に勧告、企業名の公表等の制裁がある。)であって、私法上の効力はないとされています。仮に、ある高年齢者がこの法律を根拠に65歳まで雇用せよと主張したところで、企業としてはその要求を呑まなければならない、ということはありません。
(6) 問 再雇用希望者をグループ会社の他の会社で再雇用することもできますか。
解答 できます。グループ企業及び関連企業でも、再雇用することができます。
例えば、東京にある会社の再雇用希望者を四国に所在する関連企業で再雇用することも原則としては可能です。
平成25年6月
「役に立つ労働法の知識⑦」
本号では、平成25年4月1日から施行されている労働契約法20条(労働契約に期間の定めがあること故の不合理な労働条件の相違の禁止)についての説明です。
さて、本号は、「続々々々・改正労働契約法の解説」となります。
1 有期労働契約(期間の定めのある契約一切を言う。)の労働条件と無期労働契約(期間の定めのない契約一切を言う。一般に正社員と言われます。)の労働条件との間に相違はあっても、原則として、それは有効であるというのが、まず前提としてあります。
ただし、その相違が、有期労働契約であるが故の、しかも、その相違が不合理と認められる労働条件であれば、これは禁止というものです。新20条の趣旨です。
正社員と非正規社員との間で、労働条件に違いがあっても原則としては良いが、その相違は、不合理なものであってはならない、ということです。
では、どういう場合に許され、どういう場合に許されないのか。
(A)要件
ア 同一の使用者との間で締結された有期労働契約の労働条件と期間の定めのない労働契約の労働条件との間に、期間の定めがあることにより、相違するとき
イ この相違は、次の3つの要素(要件ではないことに注意)を考慮して不合理と認められるものであってはならないということ。
3つの要素とは、
① 職務の内容=業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度
② 職務の内容及び配置の変更の範囲(転勤、昇進等の人事異動や本人の役割の変化等)
③ その他の事情(労使慣行など。例えば、定年後の労働条件の相違等)
以上です。
ウ これら3つの要素を総合評価して、不合理かどうかが判断されます。
使用者の人事政策、処遇体系、労使関係のあり方等の全体のなかでの判断となります。
正社員と非正規社員との間では、「仕事の内容が違う」、「責任の度合いが違う」、「転勤の有無が違う」などの事情があれば、それに伴って、労働条件に相違があっても「不合理」ではないとされるわけです。
60歳定年後の再雇用者である有期労働契約者の労働条件と定年前の無期雇用契約者(正規社員)の労働条件と相違していても、定年の前後で、職務の内容、責任の度合い等に違いがあることは一般的ですから、特段の事情がない限り、不合理ではないと解されます。
(B)効果
この禁止は、民法的効力を有するものであると解されています。すなわち、不合理な労働条件であればこれは無効となるということです。
無効となれば、その部分の定めはどのようになるのか、という問題があります。無期労働契約の労働条件と同じになると言うことで良いかという問題です。基本的には、無期労働契約の労働条件と同じになると解されます。それを受け入れられないという場合は、別途就業規則等でその旨を定める必要が生じます。
また、このように禁止されるような労働条件で有期労働契約を締結した使用者は、労働者に対して不法行為を理由に損害賠償をしなければならないとも解されています。
では、具体的には、どのような労働条件が有期労働契約であるが故の不合理な労働条件として無効となるか、ということです。
次の点について無期労働契約者には認めているが、有期労働契約者には認めないという場合は、有期労働契約であるが故の不合理な労働条件に当たるとして問題とされます。
① 通勤手当の支給
② 社員食堂の利用
③ 福利厚生
④ 出張旅費の支給
⑤ 健康診断
⑥ 病気休業
⑦ 社内行事への参加
皆さんの会社では、どのような処遇になっているでしょうか。仮に、相違があるという場合には、職務内容、責任の度合い、その他の慣行等からして、「不合理」かどうかをチェックしてみましょう。
平成25年5月
「役に立つ労働法の知識⑥」
さて、本稿は、前号の続きですので、「続々々・改正労働契約法の解説」となります。
本稿では、有期(期間の定めのある)労働契約を労働者の意思で、無期(期間の定めのない)労働契約へ転換できるという制度(平成25年4月1日以降施行の法18条)について、です。
(A)要件
ア 同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約であること。
同一の使用者とは、契約の当事者たる法人、個人を指します。グループ内にあっても異なる法人は同一使用者とは 言えません。もっとも、この法律の規定を脱法するためにグループ間で契約社員を回すことは許されません。
「2以上の」とありますので、有期契約は1回は更新されていなければなりません。したがって、最初から契約期間が6 年と定まっているものは、更新がないので「5年超」として、無期転換権を行使することはできません。
イ 通算契約期間が5年を超えること。
起算は、平成25年4月1日以降の契約からです。それまでの契約期間は算定されません。平成25年3月31日までに締結した有期契約の期間は算入しないということです。
空白期間があるときは、その前の契約期間は算入しません。例えば、1年の契約なら、途中で契約が終了している場合、その期間が6か月以上であるときは、前の契約期間を算入しないということです。再度の契約の時から仕切り直しです。
人事管理を戦略的に考えて、有期を無期に転換されたくない、という場合は、有期契約を「5年超」となる前に、途中で 契約を終了させるということが起こり得ます。
ウ 労働者が無期に転換する旨の意思を表示すること。
労働者が契約の期間が満了する日までの間に、満了日の翌日から無期の労働契約の締結の申し込みをした場合には、無期の労働契約になるということです。この点は極めて重要です。会社側の受諾の意思表示がなくとも、「承諾したものとみなされる」ということです。すなわち、使用者は、転換の意思表示を受諾しない、ということはできないということです 。
なお、無期転換の場合は、前稿で説明したような、更新の場合と異なり、「満了後遅滞なく、期間の定めのない契約の 締結の申し込みをした場合」は規定されていないため、労働者は、必ず、期間満了日までに転換権を行使をしなければならず、期間満了後には、転換権は行使できないということになります。無期転換権は、その期間満了までに行使をしないと消滅するということです。
ただし、「5年超」の有期契約を一旦更新すれば、新たに「5年超すなわち6年超」の有期契約となりますので、この新しい有期契約の期間満了日までに再度、無期転換権が発生します。ここが重要です。
6年目の更新が転換権の行使なく行われた場合、7年目中に新たな転換権が発生すると解されます。最初の5年超の期間中だけでなく、その後の更新期間ごとに発生するものだからです。法律は、最初の「5年超」の有期労働契約期間に限定していないからです。
使用者としては、無期契約転換申込権を行使するのか、行使しないのかを早めに知り、雇用対策に備えたいというとき、催告することができるか、という問題があります。この程度はできるという説と、法律に規定がないから、できないという説があります。労働者が使用者の催告に対して、権利行使をしない旨を明確にしたときは、無期転換権の権利の放棄として取り扱うこととなります。
(B)効果
上記のように、使用者は、当該無期転換の申し込みを承諾したものとみなされます。
この場合、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で期間の定めのない契約となります。この点も極めて重要です。無期契約になっても、身分は変わらず、正規労働者になるわけではありません。あくまでも契約期間の定めのない非正規労働者となるというものです。
今後、このような新しい労働者に対して適用すべき就業規則を新たに作成するべきかどうかということを使用者としては考えておかなければなりません。
就業規則は、使用者がすべての労働者に対して作成する義務があるからです。新たな無期労働者に対する特に定めた就業規則がない場合は、正規労働者に対する就業規則が適用されることとなりますが、それで良いかということです。
有期契約労働者の労働条件のまま、無期契約の労働者になるので、正規労働者と異なることがあれば、その旨の就業規則を作成すべきこととなります。
なお、「別段の定め」をすることは許されますので、無期契約になったことから、新しい労働条件に変更することはできます。
無期契約期間は、有期契約の満了日の翌日から始まります。
労働者、契約の種類に限定はありません。高年齢者を有期契約している場合も適用されます。60歳定年で一旦退職し、有期契約を締結し、5年目に無期に転換できるか、という問題があります。「5年超」になっていませんから、法的には無理ということになります。また、使用者は、一般的に高年齢者の再雇用の場合でも、上限を65歳までしか雇用しないと決めているものと思います(このように決めていないと終身のように解されますので、要注意です。必ず、再雇用の場合の上限を65歳と規定しておくことになります。早期退職勧奨で55歳で退職し、その後、1年毎の有期契約を更新してきて、5年超の61歳で無期契約の転換権の行使をして無期に転換したら、終身雇用になるのか、という問題があるからです。)。
育児、介護休業期間は、「5年超」の契約期間に含まれますので、その間「勤続」していないとしても、無期契約に転換できると解されます。
平成25年4月
「役に立つ労働法の知識⑤」
昨年8月10日に改正された労働契約法についての続きの続きです。
有期労働契約社員を抱えている使用者にとっては、この改正の内容については知っておいた方がよく、しかも、本稿で取り上げる改正部分は、昨年8月10日に既に施行されております。
有期労働契約者のうちの50%はパートであり、20%はアルバイトであると言われています。皆さんの会社ではどうでしょうか。有期労働契約者は、その他に契約社員、嘱託などを含み、いわゆる非正規社員と言われています。
1 使用者は、有期労働契約の期間が満了する際に、更新をするか、更新をしないかを判断しなければなりません。
更新する場合は、原則として波風は立たないのですが、更新をしない場合(更新拒絶、有期労働契約の場合はこれを雇い止めと言います。)に問題が生じます。労働者にとっては、就職先を失いますし生活の糧を失いますから、路頭に迷うことにもなりかねないからです。
2 有期労働契約の更新拒絶(雇い止め)については、これまでに最高裁判決等による裁判法理が構築されています。改正労働契約法18条(平成25年3月時点)は、この判例法理を法定化したものとされていますので、これまでもこの判例法理に従い有期労働契約者に対する雇い止めしてきたのであれば問題はありません。
3 本稿では、改正労働契約法18条(平成25年4月1日以降は、19条となります。)の要件と効果について取り上げます。
(1)18条の運用の実際
1号は、東芝柳町事件をモデルとした規定
これは更新を繰り返し、期間の定めのない契約のようになっているもの
2号は、日立メディコ事件をモデルとした規定
更新の繰り返しはないが、更新が期待されるとの合理的な理由があるもの
(2)1号又は2号に当たるものには、雇い止めが必要となり、この場合、解雇権濫用法理が類推適用されるということです。
すなわち、契約期間が満了したので、終了です、というだけでは足りず、解雇するに足りる前稿で説明した2つの要件を満たすことが必要となるということです。
(3)では、更新を1年毎に行うが、最長3年と合意し、その満了とともに有期労働契約が終了するということはできるのでしょうか。これは、可能ということになります。
その場合は、
ア 臨時性を明白にすること。例、工場廃止まで、工場移転まで、業務の廃止まで、のように。
イ 最初の契約締結時に、更新限度の絶対性を確認合意すること。
有期労働契約締結時に、1年毎に更新するが、最大3年とするという内容の「期間確認合意書」を取り交わすことです。ここで、大事なことは、その例外を作らないということです。
そうすると、1年毎に更新を繰り返しても3年になったときは、3年の期間満了により終了とすることができます。
この場合、4年目の更新の期待は、合理的なものとは認められないということです。
この「期間確認合意」は契約の当初に行うべきです。
学校法人立教女学院事件の東京地裁平成20年12月20日判決(労判981・63)は、2年半経過後になってから、3年以上更新はしないという申し入れをした事案では、3年経過後の更新の期待はなくならない、とされています。すなわち、これを理由には更新拒絶はできないということになります。契約当初にこのような合意をしなければならないということです。
(4)期間の更新を期待させるという具体的な例としては、書面に、次回「原則として更新する」という記載がある場合、あるいは、面接時に、「一応期間は1年となっているが、更新があるので」などと言っていると期待を抱かせたと認められますから要注意です。
4 では、改正18条の要件と効果ですが、
(1)要件は
ア 労働者が、
① 期間が満了する日までの間に、有期契約の更新の申し込みをした場合
期間満了までにしなかったとしても、
② 期間の満了後遅滞なく、有期契約の締結の申し込みをした場合
更新がされるということです。
イ 使用者がこれを拒絶する場合には、解雇権濫用法理の類推適用があり、更新拒絶するには、前稿で説明した2つの要件(客観的合理的理由と社会通念上の相当性)を満たさないと拒絶できないということになります。
労働者からの更新を拒絶できないということになると、
(2)効果
ア 「従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申し込みを承諾したものとみなす。」となります。
イ したがって、使用者は承諾をするまでもなく、更新の擬制がされ、有期労働契約ではありますが、従前の労働条件の同一性は維持されたまま、しかも期間の定めも同一のまま、有期労働契約が更新されることとなります。これが効果です。
5 労働者の更新の申し込みは、積極的なものを要せず、使用者から「今回は更新しない」と言われたことに対して、労働者からの異議を述べることでも足りる、とされていることは注意を要します。労働者から「更新拒絶の通知には応じられないとか、不服がある」とかいうだけでも申込みをしたこととなり、解雇できるだけの要件がないと、承諾したものとみなされるということになります。
平成25年3月
「役に立つ労働法の知識④」
昨年8月10日に改正された労働契約法についての続きです。
契約社員を抱えている使用者にとっては、この改正の内容について知っておかなければならず、しかも、一部は、昨年8月10日に既に施行されており、残りはこの4月1日から施行されますから、その対応策としても取り上げるべきものと考えた次第です。
さて、今回の号では、前号の続きを取り上げます。
1 経営戦略としての人事のあり方、労務管理のあり方等について
人事・労務管理のあり方としては、私は、次のような3つの原則を考えています。
①戦略的な人事・労務管理
②十分な教育と指導
③毅然たる措置
以上です。
①の「戦略的な人事・労務管理」とは、会社は、どういう人を採用するか、採用しないかはその自由があるため、採用において戦略を立てるのは当然として、広く法を知ること、法律を守る、法の仕組みに従うことも含まれます。その意味で、頻繁に行われる労働法改正も考慮しなければなりません。
②の「十分な教育・指導」とは、せっかく採用したからには、その才能を最大限引き出すべく十分に教育・指導をするということです。会社の歴史、伝統、技能、ノウハウ等を先輩から後輩に伝承し、これを承継させていかなければなりません。 採用した以上は、ほったらかしにはしないということです。
③の「毅然たる措置」とは、どう教育・指導しても、また注意しても改善の余地がないのであれば、やむなく一定の措置を講じるのも使用者としては当然のことです。懲戒処分、解雇等の措置を執ることに躊躇はできません。経営者の覚悟を示す場面です。
毅然たる措置を執れば、法的紛争に発展することがあることもやむを得ません。
しかし、日頃からコミニュケーションを取り、信頼関係を構築していれば、酷い結果を避けることができます。
信頼関係を構築することなく、「毅然たる措置」だとして一方的に厳しい措置を執ったとしても不平・不満が残るだけです。納得を得られません。ここが大切です。
2 有期契約社員が、無期契約社員に転換できるのは、今後5年間を超えてからですから、先の話ということです。しかしながら、その間、手を拱いていて良い訳ではありません。契約社員に対し、今から教育・指導を行い、無期契約社員に転換する際に、場合によっては、正社員にすることも考えなければなりません。この5年間は、その見極めをする貴重な時間を法から与えられたと受け止めるべきでしょう。
3 そもそも有期労働契約とは、原則として
ア 期間が満了すれば、雇用関係は終了することになります。
イ ところが、実態を踏まえると、更新を繰り返しており、あたかも無期と同じような契約があります(更新を繰り返してはいないが、更新を期待させている有期契約もあります。)。
2) 有期契約の期間中の解約については
ア 双方とも期間中は解約ができないという制限があります。
イ ただし、「やむを得ない事由があるとき」にのみ解約できます。
したがって、使用者が同意しない限り、有期契約社員から期間途中で一方的に辞めたいと言われても雇用関係は終了しないというのが法の建前です。
使用者は、辞めたいという社員を留めて置いても無意味と考えるから、同意しているものと考えられ、この同意によって、合意解約となるわけです。
3) 他方、期間の定めがない契約は、本来は、いつでもいずれからでも解約できることになります。
使用者には、解雇権があり、労働者は退職の自由があるということです。
そこで、使用者には解雇権濫用法理(判例法理からの法定化がこの度の改正で行われました。)で、解約を制限する法理ができました。そのため実際には、解雇は困難という受け止め方をされているわけです。
4 解雇権濫用法理とは、使用者には、解雇する権利はあるのですが、解雇するには、2つの要件を満たさなければならず、このひとつでも満たしていなければ、解雇は権利の濫用として、無効となるという法理のことです。
次の2つの要件です。
①客観的に合理的な理由のあること(就業規則上の解雇事由該当性が客観的に認められること)。
②社会通念上相当と認められること(大事なことは、①の要件が充足されたことを前提にしているということです。そもそも①の合理的な理由を欠いている場合は、無効です。)。
この社会通念上の相当性とは、どういうものかと言いますと、労働者の情状、注意、処分歴、改善の見込み、解雇回避措置を講じたか、他との均衡(バランスが取れた措置かどうか)、手続等の適正さ満たしているか等を総合勘案して個別的・具体的に判断されるということです。仮に合理的な理由を備えていても、この社会的相当性を欠く場合には、この点で解雇が無効と判断される例は多々あります。
今回の労働契約法改正により、契約社員の更新拒絶(雇い止め)については、解雇そのものではないので、解雇権濫用法理(労働契約法16条に規定)がそのまま適用されるのではなく、解雇権濫用法理が類推して適用される、ということを明文をもって規定したということです。解雇権濫用法理より解雇権濫用法理の類推適用の方がやや緩やかな判断がされるという解釈はありますが、それでもハードルは高いと受け止めるべきでしょう。
平成25年2月
「役に立つ労働法の知識③」
今回は、学生アルバイトの労働問題を中断し、昨年8月10日に改正された労働契約法について取り上げます。
多少とも契約社員を抱えている使用者にとっては、この改正の内容について知っておかなければならず、しかも、一部は、昨年8月10日施行されており、更に残りはこの4月1日から施行されますから、その対応策としても今回の号で取り上げるべきかと考えたものです。
1 今回の改正は、労働契約法18条から20条の新設となります。そこで、その解釈、今後の運用のあり方等について、その概要を紹介することとします。
(1)新制度の創出は、次の3つです。
①有期労働契約の無期労働契約への転換→平成25年4月1日施行
②雇い止め法理の法定化 →平成24年8月10日施行
③有期であることによる不合理な労働条件の禁止→平成25年4月1日施行
(2)この原稿を書いている平成25年1月18日時点では、新18条(雇い止め法理の法定化)の条文が既に適用されています。この条文は、4月1日以降は19条になります。ややこしいですね。
現時点でも有期労働契約者についての雇い止めは、新18条1号、2号の規定を適用することとなりますので、現在、契約社員を雇い止めしようとする場合は、この新規定を適用することとなります。もっとも、この規定は、これまでの判例法理を条文化したということになっていますから、これまでの考え方で対応すればよいことになります。
(3)改正により慌てることはない。
①契約社員の雇い止めについては、従来の判例法理は行き渡っていますので、この取扱を遵守することで良いからです。もっともこのことを理解していないと紛争の原因になる恐れがあるとは思います。
②有期契約から無期契約に転換できる契約は、平成25年4月1日以降に締結された契約が通算して5年超えてからだからです。
③有期契約であること故の不合理な労働条件の定めをしていれば、この条件は無効となりますが、このような不合理な労働条件で合意しているかどうかは至急見直しをしておいた方が良いと言えます。例えば、契約社員に対し、「あなたは契約社員だから、社員食堂を利用することはできない」というようなことがありますと、4月1日からは、その部分は無効となって、正社員と同様の扱いをしなければならなくなるとともに、場合によっては、そのような差別的な不合理な条件を付した使用者には不法行為責任があるとして損害賠償が請求されることになるかもしれないからです。各社の契約社員(パート、アルバイトその他契約社員に適用)のための各契約書についてその内容を検討し、このような意味での不合理な条件が付されているかどうかをこの3月31日までには検討し、そのような条件がある場合には改めれば良いからです。
(4)有期から無期への転換について、法が5年の猶予をおいたのは、その間に十分に用意しなさいということであると理解すべきですから、「慌てる必要はない」が「今から対策を考えておく」ことは必要と思います。戦略的労務管理の観点からすれば、当然の要請です。
有期(期間の定めのある契約)から無期(契約の定めのない契約)になる新しい労働者に適用すべき労働条件をどのように設定するか。戦略的人事・労務管理の観点からは、どうしても必要です。正社員用の就業規則、契約社員(パート)用の就業規則は当然として、今後、この有期から無期に転換した社員用の就業規則も作らざるを得ないかも知れません。正社員と全く同じにはできないと言えるからです。
法は、有期から無期に転換する場合、労働条件は同一で良く、ただし、期間の定めだけはないものになるというのですから、パート社員はあくまでもパート社員で良く、非常勤社員はあくまでも非常勤社員で良いこととなります(もっとも、この際、正社員にしようという場合、別段の定めをすれば、可能です。)。
これまで1年毎更新のパート社員が無期のパート社員になる、という労働条件を思い浮かべてください。どのような労働条件にするのが妥当と考えられますか。
賞与はどうしますか。退職金はどうしますか。有給休暇はどうしますか。転勤はどうしますか。配置替えはどうしますか。昇進はどうしますか。いろいろな問題があり、どのように制度設定を構築すれば良いのかを真剣に考えないと行けないものと思われます。
(5)今後も有期社員は必要であり、そのような業務は存続していくはずです。
有期契約がこれまでどのように活用されてきたかを考えてみる必要があります。
使用者としては、労働力の短期的、臨時的な需要への対応として、また、期間満了で終了させらるという点で雇用調整をはかる場合に利用してきたものと言えますが、このようなことは今後も当然続くこととなります。
そこで、今後は、有期労働契約の締結(契約社員等)について、どう考えて運用していくかは、極めて重要な経営の戦略でもあることになります。
平成25年1月
「役に立つ労働法の知識②」
使用者は、法律を守らないと罰則を受けるというのが労働基準法の建前ですから、使用者側は、注意を要します。労働基準法上、労働者が罰則を受ける規定はありませんが、労働者の親が罰則を受けることもあるということは前回取り上げたとおりです。
さて、今回は、次の小問から始めましょう。
③未成年の学生アルバイトに支払うアルバイト料は、一体誰に払うべきでしょうか。その父親が、子を思う心配のあまり、しかも、学費は親である自分が払っているのだからと言って、使用者のところに学生アルバイトに代って、親権者としてアルバイト料の支払いを求めてきたときは、使用者は父親に払うのでしょうか。さあ、いかがでしょうか。
この点についても未成年者の労働者については、労働基準法は特別な規定をしています。すなわち、労働基準法59条は、「未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはならない。」と。したがって、正解は、使用者は父親に払ってはならないということになります。
使用者が父親に支払うと、使用者は罰則を受けます。30万円以下の罰金です(同法120条1号)。
驚くことに、支払った使用者ばかりでなく、支払を受けた父親も罰則を受けることとなります(同法120条1号)。
労働基準法は、これだけ労働者を保護しているということになります。
ついでに、賃金支払いの5原則を取り上げておきます。この点は重要なのでこれから何回か取り上げることとなります。
賃金は、労働者にとって生活の糧ですから、その支払いについては法律で確保できるように厳しく規定しています。これに反すると使用者は30万円の罰金です(同法120条1号)。
④学生アルバイトに対し、今月は、暇で、仕事がなかったからという理由で、今月分のアルバイト料は、翌月に延ばし、ふた月分をまとめて支払う、ということができるのだろうか。さあ、いかがでしょうか。
この点については、労働基準法24条に規定しています。すなわち、同条1項は「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。以下、ただし書の規定は省略」と。
同条2項は、「賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。以下、ただし書の規定は省略」と。
①通貨で
②直接労働者に
③その全額を
④毎月1回以上
⑤一定の期日を定めて賃金を支払わなければならない。
以上の原則のことを賃金支払いの5原則と言います。
すなわち、
賃金は、日本国内で通用する貨幣で支払うこと(ただし、例外はありますが、今回は省略します。)、
労働者に直接支払うこと(親とか代理人とか、債権者に支払ってはならない。)、
その全額を支払うこと(賃金から勝手に差し引いてはならない。)、
毎月1回は支払うこと(年俸制であっても12回に分けて支払わなければならない。)、
一定の期日を定めて支払うこと(特定の日を決めて支払わなければならない。)
となります。
法は、このように労働者の生活の糧である賃金の支払いを規制し保護していることになります。
学生アルバイトは労働基準法上の労働者です。労働者に適用される同法24条の規定は当然に学生アルバイトにも適用されることとなります。学生アルバイトだからということでこの原則に反することはできません。
したがって、使用者は、学生アルバイトに対し、毎月1回は支払う必要があり、これをふた月分まとめて支払うということはできません。