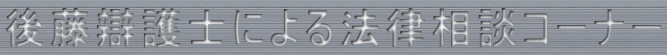
| かけはし誌上コラム(かけはし掲載分) | 羽田鉄工団地協同組合 |
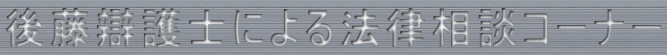
平成28年12月
「有期雇用契約社員に対する対応」
改正労働契約法18条が新設され、平成25年4月1日以降の有期雇用契約を締結した社員につき、3年8か月ほどが経過しましたので、あと2年4か月ほども経ちますと、契約社員の無期化の可能性が出てきました。この制度は、契約社員、パート社員、定年後再雇用の高年齢者にも適用されます。平成25年4月1日以降の有期雇用契約を締結した契約で、更新を続けてきたものについては、平成30年4月1日以降に無期化の問題が出てきます。不合理な労働条件の相違(同法20条)についての具体的な裁判例も出てきていますので、この時期に一度取りあげ、それに対する備えを喚起しておきたいと思います。
1.労働契約法18条(無期化)について
(1)平成25年4月1日以後に有期の労働契約を締結したケースに適用されます(その前の契約の期間はカウントされない。)。
(2)同一の使用者間で契約したものに限られます。
問題は、グループ間で契約のやりとりをした場合です。通算5年の期間を免れるためという脱法行為が明白であれば、偽装として無効とされ、この場合は「同一の使用者」に当たると扱われます。
(3)2つ以上の契約の期間の通算が5年超したことが必要です。すなわち1回は更新した場合をいいます。
法文上は、「繰り返した」という規定ではないので、契約を繰り返したというより、契約期間が更新され、その通算が5年超であることで足りるということです。
回数が5回超ということではありません。途中契約が切れているような場合、空白期間(ただし、6か月以上が必要)があると言いますが、通算5年超にならないので、もういちどやり直しになります。
仮に、有期契約の期間が1年であるとすると、5回目の更新後の契約の満期日までに、労働者がその満了日の翌日からの契約について期間の定めのない契約の締結をしたいと申込をしたときは、使用者は承諾したものとみなされ,無期の雇用契約が当然に成立します。
例。平成25年4月1日に有期雇用者として1年間の契約を締結し、以後更新し続けて平成30年4月1日にも更新した場合、この契約の満了日である平成31年3月31日までの間に、3月31日の翌日である4月1日からの更新後の契約について、期間の定めがない契約をしたいという意思表示が労働者からされますと平成31年4月1日からの契約は無期契約となります。
(4)無期化した契約の労働条件は、現に(直前に)締結している契約の労働条件と同一となります。例えば、パートであるとの身分は変わらず、賃金、勤務内容、勤務場所、労働時間等も変更をすることなく、更新することとなります。
ただし、契約内容の変更をしたいときは、当事者間の合意でできます。
無期化しても身分は変わらないというところに特徴があります。
(5)通算期間は労働契約が存在していればよく、育児休業、介護休業、研究休職、あるいはその他の理由で休職していても,その期間は通算期間に含まれます。
(6)予め、労働者に無期の申込をすることを放棄させることは公序に反して無効となります。ただし、5年超になり、無期の申込みができるようになってから放棄させることはできますが、次回には再び、無期の申込みができることになります。
(7)無期化に備えた使用者側の対応
①単純無期化制度を認める。
②限定正規社員化
職務限定、勤務地限定、勤務時間限定などして、正規社員化する。
③完全正規社員化
人手不足等を考慮して正規社員化を図る。ただし、その場合の基準をどう設定するかが問題となります。
(8)無期化した社員のための独自の就業規則の制定の必要性があります。
就業規則を作成していないことによるリスクは、使用者が負うこととなります。
2.労働契約法19条(雇い止め)について
(1)有期雇用者の契約が①「反復更新された契約」であって、その契約を終了させることが、契約の定めのない正規の社員に対してならば、解雇の意思表示をするしかないと社会通念上同視できる場合、②次回更新されると期待することについて合理的な理由がある場合には、簡単には雇い止めはできません。解雇法理が類推適用されます。
(2) 契約の期間の定めをするとその途中で辞めさせることはできないのが原則です。期間途中で契約を解約するには「やむを得ない事由」が必要となります(民法628条)。
「やむを得ない事由」とは、一般的には、解雇理由とか懲戒解雇理由を指します。
(3)解雇法理が類推されるということは、労働契約法16条の要件を満たすことが必要であるということになります。また、懲戒解雇要件が必要となる場合は、同法15条の要件を満たすことが必要となります。この場合、次の要件が必要となります。
①客観的合理的理由があること
解雇規定や懲戒処分規定に該当する事実があること
②社会通念上相当であること
①の事実があるだけでは足りないことに注意しなければなりません。社会通念上相当であると認められるかどうかは、一般的に、違反の程度が重大であること、何度も注意したこと、反省が見られないこと、改善の余地が見られないこと、処分歴、調査に対する態度が不誠実であること等に照らして、解雇(懲戒解雇)となってもやむを得ないという大方の人が思うような場合であるということになります。
(4)将来、無期化した場合は、期間満了での終了ということはできなくなりますので、無期化後の雇い止めの基準は、厳格に規定しておく必要があるということになります。
(5)実際には、無期化に備えて、問題となるような有期契約社員には、更新を約束しないこと、問題行動があれば、看過放置せず、その都度注意すること、改善に向けての一筆貰うなどの工夫が必要といえます。争われても支障がないように、記録化すること、履歴が残るようにすることも大事です。当該本人からも内容確認のサインを貰うといった工夫も必要となります。
3.労働契約法20条(不合理な労働条件の相違の禁止)について
(1)契約期間があることによって労働条件に不合理な相違があると判断されますとその労働条件は無効となり、契約期間の定めのない社員のそれと同じ契約内容となります。また、故意過失があって、そのような相違ある契約をした使用者には、不法行為に基づく損害賠償責任が生じる場合があります。
(2)したがって、不合理な相違とならないように、労働条件を設定しなければなりません。
法は、①業務の内容及び業務の内容に伴う責任の程度(これを「職務の内容」という。)、②職務の内容及び配置の変更の範囲(人材活用の仕組みと言います。)、③その他の事情を考慮して不合理な相違かどうかを判断すると規定しています。
③その他の事情とは労使慣行のようなものが含まれます。例えば、定年後の再雇用の場合の給料は定年前に比して減額となるなどの事情を言います。
これらの3つの事情に照らして、他の契約期間の定めのない正規社員と異なる労働条件を決めた場合は、不合理な相違とは見られません。
(3)一般には、通勤手当、出張手当、食堂の利用、安全管理、福利厚生施設の使用、災害補償、服務規律、教育訓練、健康診断、病気休業等、内部の行事への参加等の違いが不合理な相違かが問題となります。退職金の支給がないのは、不合理な相違とは見られませんが、通勤手当、出張手当、食堂の利用、安全管理、福利厚生施設の使用、災害補償などで相違がありますと、不合理な相違とされることが多いと言えます。
以上
平成28年11月
実際にあった裁判事件シリーズ」(ある旅行代理店との闘いで勝利した事件)
本件のようなケースは、珍しいものではあろうと思うが、旅行される方も多いかと思われますので、ご参考に供したく、また、裁判実務にも何程かの寄与出来たものと考えるので、本号ではこのケースを取りあげることとした。
1.Fさん家族4人は、平成24年3月2日、モン・サン・ミッシェルの全景を対岸のルレ・サン・ミッシェル(以下「ホテル」)に宿泊してその敷地から眺めること、また、「時間とともに姿を変える神秘的な景色」を楽しむ等のために旅行契約を締結した。しかも、パンフレットにはその旨の記載があること、旅行代理店にもそれが確約されているのかを念のために確認したうえで締結した。
Fさん家族がそのような念を入れて確認したことにはわけがあった。Fさん家族は、前々からモン・サン・ミッシェルの全景を対岸のホテルに宿泊して眺める旅行をしたかったが、このことが確約された旅行パックはそれまでになかったうえ、Fさん家族は、モン・サン・ミッシェルの島内は、宗教施設(お墓)があることから、ここに宿泊することを嫌っていたからである。モン・サン・ミッシェルの島内にて宿泊する旅行はいくらでもあったが、島外のフランス本土のホテルに宿泊し、そこからその全景を眺める事が確約されたパック旅行はこれまでになかった。
「西洋の驚異」と言われるモン・サン・ミッシェルを対岸から眺められることが可能と考えられていたFさん家族にとって、想定外の出来事が起きた。ホテルに到着する2日前になって、ホテルから、ある団体の人数が増えたことによって、それまで予約し宿泊を期待していたFさん家族らを含む一行は全員、ホテルに泊まれず、追い出されることとなった(これをキックアウトといいます。)。単純なダブルブッキング(予約の重複)ではありません。そのため、予定されていた6月15日にはホテルに宿泊することができなくなり、「時間とともに姿を変える神秘的な景色」を楽しむこともできなくなった。むしろ、もっとも嫌っていた島内の代替ホテルに宿泊せざるをえなくなった。
Fさん家族は、これは旅行契約の重大な違反である、自分達は、モン・サン・ミッシェルを対岸から眺められることの確約をとって旅行契約をしたものであるから、この内容が履行されない限り、旅行の意味はなく、全部不履行であるから、代金全額を返還せよ、という主位的請求をし、予備的に、ホテル側の事情で、宿泊できなくなったこと等から、旅行代理店には契約の不履行がないとされたとしても、旅行者に対して、尽くすべき信義則上の注意義務を怠ったから、不法行為責任があり、Fさん家族が蒙った慰謝料を支払えという請求をすることになった。
珍しいというのは、このような事案で、精神的苦痛を理由に提訴までする旅行者はいないと思うからである。返還を求める旅行代金と弁護士費用を含む法廷闘争費との釣り合いが取れないし、旅行契約には約款が適用され、ダブルブッキングの場合は、一律に、2パーセントの補償をすれば、旅行代理店は責任を免れるとしているから、旅行客も二の足を踏むのである。ダブルブッキングの場合の補償金の支払いは、旅行代理店は、保険に入っているので、躊躇なく支払を提示する。本件でも、旅行の途中ですでに2パーセントの補償金の支払いをするとして、用紙に書き込むことを求めている。
Fさん家族は、そもそも本件はダブルブッキングの事例ではないこと、キックアウトであること、ダブルブッキングに適用がある補償規定は、キックアウトには、適用がないとし、また、ホテルからキックアウトという連絡が2日前にはあったにも関わらず、これを隠し続け、宿泊当日の午後3時に現地に到着した時点で初めてその説明をし、お客がやむなく島内の代替ホテルに宿泊せざるをえない状況を作ったこと、Fさん家族は、島内に宿泊することを嫌っていたのであるが、何故、代替ホテルの選択につき、Fさん家族らの意向を全く確認もせずに、一方的に決めたのか等、旅行代理店の対応に納得できなかった。旅行代理店なら、信義則上、いち早くホテルからのキックアウトを知らせ、その理由の説明、ホテルとの交渉の有無、程度、結果、代替ホテルの有無、ホテル名等につき説明し、お客に配慮した対応をしなければならないのに、これを尽くさなかったことに社会通念上容認できないものがあると考えるに至った。実際、宿泊後の翌日午後7時になって初めて支店長がダブルブッキングでしたと説明したのみであって、キックアウトとの説明をしなかった。支店長の話によれば、旅行代理店がホテルと喧嘩すると今後二度と取引をして貰えなくなるということでしなかったというものであった。
正義感に燃えるFさん家族は、この説明や対応に全く納得できず、旅行代理店から酷い精神的苦痛を受けたとして、この点についての不法行為責任を理由に慰謝料を請求することにした。
2.裁判では、旅行契約全部につき債務不履行があるとの主張は認められなかったが、以下の諸点が考慮され、Fさん家族4人の慰謝料請求全額が認められた。ひとり当たり10万円の合計40万円を請求していたところ、この全額が認容されたものである。日本の慰謝料額は極めて低いが、全額認容するのも珍しい。
①代替ホテルを決定するにつき、Fさん家族ら旅行者の意向や希望等を全く聞かずに、「評判は悪くないオーベルジュの方が島内価値も含めて最終的にはいいのではないか」と お客の意向を聞かずに島内のホテルに決めてしまったこと。
②添乗員は、宿泊日の午後3時まで、ホテルからキックアウトされ、宿泊できなくなったことを告げず、また、夕食直前まで代替ホテルを告げなかったし、割り当てもしなかったこと 。そのため、Fさん家族らは、雨降りの中、軒下に立ったまま、代替ホテルが決まるまで放置され、惨めな思いを味うことになったこと。
③キックアウトされ、宿泊できなくなったにも関わらず、旅行代理店としてホテルとは撤回させるためなどの積極的な交渉など何もしていないこと。
④ホテルに宿泊できなくなった理由については事実を告げず、翌日午後7時過ぎころになって初めて、「オーバーブッキングでした」という説明をしたのみであったこと。
3.判決がこのような結論に至ったのは、以下のような根拠があることを考慮したことによる。旅行者の多くは、旅行代理店からの極く少額の補償金(2パーセント)の申し入れに唯々諾々として応じざるを得ない状況にあるものと思われるが、本判決は、これに警鐘をならすものとして意義がある。
ア旅行代理店は、予定のホテルに宿泊させるよう最大の努力をすべき義務を負っている。ただ努力しましたということで済むものではなく、一般的に旅行業者の平均的な能力を もって旅程管理等の義務を尽くしていたならば得られるであろう結果を得られなかった場合には、当然努力義務懈怠となると解されること。
イ旅行契約の内容を変更するには、「天災地変、戦乱、暴動、・・・略その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得 ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して」行う義務があること。
ウ旅行代理店は、「変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものになるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。」の義務がある こと。
エ旅行代理店は、「旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けら れるために必要な措置を講ずること。」及び「前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものになるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。」の義務があること。
以上である。J社は、このような基本的な注意義務を怠ったことは明らかであった。
平成28年10月
「実際にあった裁判事件シリーズ」(未成年者の面会交流事件)
1.本号は、7月号に掲載された「性格不一致を理由とする離婚請求事件」の続きです。離婚は成立し、娘の親権は妻が取れたのですが、その後も夫との間に大きな問題が残りました。それは、現在9歳になった女児との面会交流を巡っての紛争です。現在は、第三ステージにあります。
離婚後間もなくして、面会交流を巡って争われました。家裁での調停・審判があり、これに対する夫側の不服申立てにより高裁に係属し、高裁での決定がされたのが第一ステージです。
もとより、妻側は、父親と面会させることに基本的に賛成していますので、高裁決定に基づき面会交流をしてきましたが、女児は、成長するにつれて、面会を拒否する意思を表明するようになりました。1歳ころに別居していますので、父親を知りませんし、面会しても楽しくも面白くもなかったのでしょう。それでも決まったことだからと、妻は面会させることに努めてきましたが、どうしても嫌だと言って女児が全く面会を拒否することになりました。女児の意思を尊重するならば、もう少し大きくなってから、面会交流することにしようという妻の意向を理解して夫からもこれに応じて貰えるかと思ったのですが、女児がこのような態度を取っているのは、妻の入れ知恵に違いないと勘違いした夫は、絶対に譲らず、面会交流決定違反であるとして再度の調停を申立てました。他方、妻側も女児の意思を尊重すべきだ、面会を再開するにしても、女児の意思を尊重したものにすべきである、との主張をして、前記決定の変更の申立てをしました。これが第二ステージです。これも調停・審判と進み、夫側の不服申立てにより再度、高裁に係属し、高裁の決定が下りました。現在は、この2回目の決定に基づいて面会交流が予定されていることになります。
ところが、女児は、やはり父親とは面会したくない、面会したくなったらその時は必ず面会するから、と言って、再び面会を拒否するようになりました。第二ステージでは、夫もある程度は女児の意思、意向を尊重することは約束したのですが、根底には、妻に対する不信と、自分には父親としての権利があるという思い、裁判所で決定されたことは守る義務があるという気持ちが強いため、なかなかこの現状を受け容れてくれません。子どもは物ではないので、しかも、9歳ともなれば自己の意思をはっきりと表現しますから、直接、その旨を伝えました。これが現在のステージということになります。
そもそも、離婚自体の解決に難航した事案ですから、その後の紛争として子の面会交流を巡っての紛争が続くだろうとは推察されます。このように離婚後も根底に争いが残っている夫婦のことを「高葛藤夫婦」と言いますが、このような場合の子の面会を巡る争いは深刻となります。
2.私は、妻側の代理人ですから、この面会交流を巡っては、大岡裁きの例を思い出してしまいます。ふたりの女性にどちらが母親かを判断するために子どもの腕を引っ張らせた事案です。それぞれが私が母だ、私の子どもだ、と主張し、子どもの腕を引っ張ったところ、子どもが痛がって泣いてしまった、一方の女性はさらに強く引っ張り、他方の女性は、引っ張るのを止めたので、引っ張り続けた女性が勝ったといってその子を連れ去ろうとしたとき、大岡裁きでは、ちょっとまてと、本当の母親なら子が痛がったら引っ張るのを止めるのが母心だろうと、逆に腕を引っ張ることを止めた女性の方を母親と裁いたという言い伝えです。親心を理解するうえで、格好の例だと私には思われます。
親なら、何よりも子どもの人格を尊重し、その意思、意向を大事にするのではないでしょうか。それでなくては、折角の「子の利益のために」「子の福祉のために」という面会交流を実現することはできません。父親としての権利を優先させるよりもまずは子の立場を考え、子の意思を尊重すべきではないでしょうか。
3.最近の傾向ですが、父親の方(男性側)から子と面会したいとの希望が出される例が増加しています。この協議が成立しなければ、調停、審判の申立てがされる事例も急増しています。
親権者となれなかった親から親権者となった他方の親に対して子と面会することを求める法的根拠は何か、が問題になります。親であるからその権利があるかのように誤解されているのですが、親だからと言っても面会交流する権利が発生するわけではありません。養育費を払っているからと言ってもこのような権利が生まれることもありません。
面会交流が認められるかどうかは、「子の福祉に適うか」「子の利益のためになるか」の観点から判断されます。
常識的には、未成年者でも立派な人格を有しているのであるから、その意思や意向を尊重すべきだし、その意思を無視したやり方では、面会交流の意義は没却され、意味がなく、むしろ、弊害ばかりではないかと考えられます。
子どもの意思に反する面会交流は、会いたくない人と会うことを子どもに強制することに外ならず、実現は困難であるうえ、このような面会は、子どもの精神的な成長にも悪影響があるとの実証もされています。
4.ところが、難問は夫側ばかりでないところにこの面会交流を巡る深刻な問題があります。
いま、家庭裁判所の実務は、父親像をなくさないことが、子どもの成長に必要である、したがって、非親権者である父親も父であるから、親権者となった母は努力して未成年の子を父親に面会をさせるよう努めなさい、子との面会交流を認めることが「子の福祉」に適うという考えが基本です。
このような考えを面会交流原則的実施論と言います。「子どもが示した拒絶意思を言葉どおりに素直には受け取らず、子の表面的な言動にとらわれない。」という基本的立場にあります。
未成年の子は、物ではなく、人であり、感情を持ち、意思を持ち、1個の人間として年は若いが尊重されなければならないはずですし、その人格権も尊重されなければならないはずですが、残念ながら家庭裁判所の現在の実務の大勢は上記のとおりです。
しかし、子が拒絶しても父親との面会交流を続けさせることが子の福祉になるとの実証的根拠はなく、逆にマイナスばかりである、とする見解があるにも拘わらず、裁判所の実務に現在のところ変更が見られる兆しはありません。
家庭裁判所の実務が上記のようなものである以上、困難ではあるが、夫側に理解を求める方向に行かざるを得ないという状況にあります。
平成28年9月
「経営戦略としての事業譲渡と会社分割」
1.会社は永続しなければならないし、「会社の目的は永遠に存続すること」にあると堂々と宣言する経営者もいます。そのためには、会社の事業内容が、社会的有用性をもっていなければなりません。
そこで、単に、救済としてのそれではなく、経営戦略としての事業譲渡(事業譲受)、会社分割(被分割会社)を考えても良いのではないか、と思います。
2.平成28年6月6日付日経新聞朝刊「中小企業2030年消滅?」との記事では、14年後、日本の中小企業の社長の年齢は、80歳になる、と報じています。
経営者の高齢化等により引退もあります。後継者が見当たらず、やむなく廃業に至ることもあります。
会社の技術力が優れ、社会的有用性が高く、従業員もいるという場合には、簡単に消滅させられないのではないかと考えます。
3.日本における長寿会社の例として、ダントツは、千年企業といわれる金剛組で、578年に創業ですから、1436年も経過していることになります。長寿会社は、世界でも日本が圧倒的に多いとされています。ちなみに、200年企業は、3000社、200年を超える会社は、3013社、500年超は、39社であるとされています。
このような永続を願う風土は、日本人的な家族的経営、人を大事し、仕事を大事にする気質から来ているのかも知れません。
4.さて、事業譲渡(事業譲受)、会社分割について、です。
後継者不在(事業承継の困難性)、後継者に不満足、後継候補者の能力不足等(創業者のカリスマ的能力に到底適わない)、後継者を巡る権力闘争等(親子間や派閥間の闘い。創業家と経営者間の闘いもある。)のために、事業承継を巡って激しい争いが起きることもありますが、残念なのは、事業に社会的有用性があるのに、やむなく廃業等の選択をしなければならないような場合です。一般に、人手に渡してでも残したいと考えない、また、他人の会社を譲り受けてでも事業を続けたいという経営者があまりいないのではないかという点が問題となります。
(1)事業譲渡と会社分割について
事業を譲渡する会社(譲渡元)、事業を譲り受ける会社(譲渡先)、分割会社、分割先会社と言います。
企業の買収とは、株式の売買です。雇用主体に変更はありません。株主が変わることにより経営方針が変わるかも知れませんが、労働契約の当事者に変更はありません(買収によっては、当然には労働契約内容に変更はない。)。
(2)事業譲渡について
a 事業譲渡とは、組織(事業部門、工場、支店、企業全体)を一体として譲渡することです。土地や建物をバラバラにして売るのではありません。事業譲渡は一種の売買(特定承継)で、合併(包括承継)ではありません。
b 売買ですから、内容は、合意で決められます。ただ合併と異なり、譲渡元の会社は存続します。
c 労働契約の承継問題があります。譲渡元の労働者(従業員)が譲渡先に異動する(承継される)か、という問題です。
有望な部門か、不採算部門か、全部譲渡か一部譲渡か、という問題もあり、労働者にとって、承継は重要な問題となります。しかし、労働法的には、当然に承継はしません。民法625条1項は、使用者は労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことはできない、と規定しているからです。労働者の同意がなければ承継させられません。労働者には事業譲渡における承継につき拒否権があるとされます(東京地裁平成9年1月31日労判712.17本位田建築事務所事件)。
d 次に、承継される労働者の選別ができるかという問題があります。通説・判例は、双方の合意により選択(人選の自由)が可能であるとされます(東京高判平成17年7月13日労判899.18東京日新学園事件)。
e では、不当に排除することは可能か、その場合はどうするか、という問題があります。組合員であるが故に排除された場合は、不当労働行為(労組法7条1号)となり、原状復帰すなわち承継があったものとされる場合があります。その他に、女子のみ、高齢者のみがそれ故に排除された場合等が考えられます。しかし、排除が不当だとしても譲渡先に当然に雇用されたとは言えないのが法理です。
勝英自動車学校事件(東京高判平成17年5月31日労判898.16)は、原則引き継ぐ合意と例外的一定の労働者の排除合意があった事案ですが、例外的排除合意は、不当であるため無効と判断したうえで、原則的引継ぎ合意のみを有効として、結果的に全員の引継ぎを認めた事例です。
実際の場面では、承継問題を避けるために、譲渡元でまず解雇し、譲渡先で新規採用する、という方法が採られるものと思います。
(3)会社分割について
a 会社分割とは、会社が事業に関して有する権利義務の全部又は一部を他の会社に承継させることを言います。合併は、もとの会社が消滅する(元の会社は消滅し、合併後の会社に全部承継される。)が、分割の場合は、分割される元の会社は残ります。そのため、会社分割は、部分的包括承継といわれます。
b どちらに権利義務が帰属するかという切り分けは、分割契約書や分割計画書によって決まります。切り分けは、組織といえないようなものでも、できます。事業に関して有する権利義務の一部であ
れば、分割の対象となるからです。
c 労働契約の承継問題があります。そのため労働契約承継法(正式名「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」)が労働者保護を目的として制定されています。全文8か条から成ります。
会社分割の場合の承継関係ですが、対象事業に主として従事する労働者は、分割先に承継され、労働者が承継されたくないと異議を申し出ることはできません。したがって、承継されない労働者が異議を申し出れば、承継されたものとされます。
上記以外の労働者は、もし分割先に承継されたことを不満に思い異議申出をすれば、不承継とされます。
d 分割しようとしている事業に「主として従事する労働者」の「主として」の判断は、労働者が従事している時間や役割で考えると解されます。
e 会社分割による承継後の労働条件
部分的包括承継ですから、合併と同様に、そのまま承継されます。ただし、分割それ自体を理由に
は労働条件を変更することはできません。実務上は、分割前に変更しておくか、分割後に変更するしかありません。
5.企業再編としての事業譲渡や会社分割の場合に、労使紛争が起きる例があります。紛争があるよりもない方がスムーズに行くことは間違いありません。スムーズに行くためには予防が必要となります。せっかくうまく承継したとしてもその後に問題が明るみに出たらなお困ることになります。
その意味でも未然に労使紛争を防ぐために、経営者にも一定の知識が必要とされるのではないかということです。
平成28年8月
「実際にあった裁判事件シリーズ」(民事交通事件訴訟)
1.本号は、事故時73歳の女性が自転車で交差点を走行中に、65歳の男性が運転する弁当を宅配中の普通自動車に横から衝突されて重症を負い、その結果(因果関係に争いがない事案でした。)2年後に死亡したという事案における損害賠償請求訴訟において、被害者側にはどれだけの損害が賠償されるのかという点を巡る裁判の紹介となります。
2.交通事故による損害賠償を巡る紛争の場合、自動車損害賠償保障法に基づく強制保険たる自動車損害賠償責任保険があり、また一般的には任意保険にも加入していることから、通常は、保険の発達により、加害者の立場でも、また被害者の立場でも、裁判にまで発展することはないと考えられているかも知れません。
3.しかし、現実には、加害者の過失の内容、程度が争われますし(被害者側にも過失があるときは、その割合の認定が争われ過失相殺という形で賠償額の減額が問題となります。)被害者が高齢者ともなれば、その損害を算定するについてはいろいろと問題があります。高齢者は就労していないので、収入がないと考えられ、その場合の損害賠償額がどう算定されるべきかという問題があります。15歳から67歳までが就労可能年齢とされていますから、67歳を超えた高齢者の場合、果たして休業損害や死亡による将来の逸失利益が認められるのだろうか、認められるとしてもどのように算定をするのだろうかという問題があるわけです。
高齢者でも現に稼働している方は現実の給与取得や事業所得を前提に算定されます。
4.本件の被害者は、73歳の家庭の専業主婦であって、パートもしていないところから、このような場合、被害者が請求できる損害賠償の内容とその金額はどうなるのかが関心が持たれるところです。加害者が任意保険に加入している場合は、真の相手方は保険会社となります。
5.裁判実務では、以下のようになります。
本事案では、受傷後に死亡したことから、生存中2年間の損害と死亡による損害との両方が考えられます。
また、損害には、積極損害と消極損害とがあり、精神的苦痛に対する慰謝料が考えられます。また、死亡により本人ばかりでなく、近親者の損害が考えられます。参考のために裁判(実際は和解で解決しました。)で認められた金額を→で示します。万未満は省略。
A生存中の被害者自身の損害
○入院費等を含む治療費(実費)→281万円
○自転車の破損による損害(査定額)→2万円
○入院雑費(入院1日当たりの一定額。1,500円が基準)→112万円
○付添看護料(1日当たり6,500円が基準。付添看護が必要と認められるとき。仮に完全看護の病院に入院中でも一定額のものは認められる場合がある。保険会社は必要性 につき争うので、付き添った証拠をできるだけ残す。)→487万円
○付添人の病院までの交通費(実費)
○休業損害(会社等に勤務する者については欠勤したために減額になった分であり、損害につき差額説を取る実務では、現実に損害がないと賠償が認められないときがあり ます。本事案のように、家事従事者は、女子労働者の平均賃金(賃金センサス)によって算定されます。要するに、家事従事者でも休業損害は認められるというところが大事 です。)→607万円
○入院慰謝料(症状と入院期間等で算定されます。)→500万円
B死亡による損害
○逸失利益(事故に遭わなければ生涯において得られたであろう利益)
給与所得や事業所得が一般であるが、家事労働も含まれ、年金等の給付金も含まれます。
被害者が55歳以上の場合 簡易生命表により求めた平均余命年数(これは厚労省で発表している平均寿命とは一致しません。)の2分の1を加えた歳となります。本事案は 死亡時75歳であり、女性の平均余命年数は15.27歳として計算。
そのうちの8年間を家事従事できる期間としてその間は、逸失利益の喪失があると考えます。→休業損害と同様に算定します。→1,286万円
その後の7年間は、年金受給権の侵害として算定します。→139万円
本事案のように、67歳を過ぎた受傷時73歳(死亡時75歳)の家事従事者でも、一定期間の逸失利益が算定され賠償されます。
○死亡慰謝料(一家の支柱に準ずる妻であることから)→2,400万円
夫固有の慰謝料、子ども固有の慰謝料も発生しますが、実務では、本人分と併せて上記のような一定額を算定しています。
○葬儀費用(墓碑建立費等を含む)→150万円(定額化されています。)
○文書料(戸籍謄本等、郵便費用、医療機関に対する診断書等の開示請求費用等)→実費
○弁護士費用→認容額の10パーセントの額
なお、夫と子どもは、被害者の損害を相続により法定相続分に従い相続することで請求することとなります。
○遅延損害金(事故日から支払完了までの間の年5分の割合による金額)
保険会社としては、解決まで日時が経過するとこの年5分の割合による遅延損害金は負担が大きくなるため、できるだけは早く解決したいと考えているようです。
なお、和解の場合は、早期に解決できるメリットも考慮されますが、裁判所は、必ずしも遅延損害金をゼロとはせず、ある程度考慮する扱いをしています。例えば、自賠責で支払われた分には損害金を付さないが、それ以外にはきっちりと計算して全額を認める扱いをするなどです。和解には互譲の精神が必要でありますが、裁判では弁護士費用も認められていますように、和解でも被害者側の立場に立った金額が算定される扱いとなっているといえます。
6.本事案のように、事故時73歳、死亡時75歳の家事従事者である女性に対しても、上記のような算定により、損害賠償額が認められるということが大事です。
自転車事故が多発している現在、事故には遭わないよう格段の注意が必要ですが、万一、事故に逢った場合には、できるだけ十全な治療をすることを求めるとともに、不幸にも亡くなったときは、できるだけ高額の金銭的補償が望まれます。本人の悔しさを晴らす必要がありますし、遺族に対するせめてもの供養となるからです。保険会社も適正迅速な解決に向けての努力はされますが、本事案でもその例に漏れなかったのですが、被害者側の過失をかなりしつこく攻めて来ました。賠償額が結構な額になるからでしょう。
本事案で、被害者の過失は5パーセントに留められました。もっともこの分は、本人が加入する保険会社から補填されます。
平成28年7月
「実際にあった裁判事件シリーズ」(性格不一致を理由とする離婚請求事件)
1.本号では、妻から夫に対する性格の不一致を理由とする離婚請求の事案を取り上げたいと思います。
小職は、妻の代理人として闘ったということになります。
夫婦間で離婚に向けての話し合いを続けたが、夫は離婚に応ぜず、非は、妻にある、妻さえ態度を改めれば円満な家庭生活が営めるというものです。時に感情的になるため双方の親が介入したり、仲人が関与したりしました。本人同士での話し合いによる解決は決裂し、妻側から小職に離婚の依頼がされました。妻は、もと有名なタカラジェンヌ、夫は歯科医。年齢差は10歳、いずれも初婚です。
2.結局、この案件は、妻側からの内容証明郵便による協議離婚の申し入れ、夫側の拒否→妻側の離婚調停申立て→夫側、離婚に応じず、不調→妻側の離婚裁判提起→裁判では、妻及び夫の各本人尋問の証拠調べ等を経て、妻側の一審勝訴(離婚を前提とした和解勧告があったが、夫側拒否。)→夫側の不服申立(高裁に係属)→控訴審では、書面審理により、二審でも妻側の勝訴(なお、控訴審でも裁判所より和解勧告がされたが、夫側が拒否。)→夫側から最高裁への不服申立てがなく、妻側の勝訴確定。
以上のような道筋を辿りながら、妻が離婚を勝ち取ったというものです。離婚とともに、もうひとつ、重要な争点であった、女児(2歳)の親権者は、妻に指定されました。その結果、夫側に一定の養育費の支払いが命じられました。
この事件の離婚理由は、暴力、不倫、仕事をしない、生活費を入れない、借金がある、ギャンブルをする、などの「形に見える」理由ではなく、性格の不一致という主観的なものであるため、訴訟上の立証に難航した事案です。それゆえ、夫側に対する離婚の説得も困難であったわけです。
3.日本における離婚の約8割が協議離婚であると言われますが、協議により離婚が成立しなければ、上記のように調停、訴訟という道筋を辿ることとなります。
協議離婚には、離婚原因の有無は、原則として不要であり、お互いに合意すれば成立するわけです。しかし、裁判離婚が認められるためには、民法770条1項1号から5号までの要件(離婚原因)があるときに限り、離婚の訴えを提起することができると規定されており、裁判では、これら離婚原因の少なくともひとつが認められなければ、勝訴しません。法定の離婚原因とは、以下のとおりです。
1号は、配偶者に不貞行為があったとき
2号は、配偶者から悪意で遺棄されたとき
3号は、配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4号は、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5号は、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
4.「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」には、暴力、酒乱、借金、ギャンブル、無断外泊、性の不調和、宗教の違い、性格の不一致その他諸々の事情が含まれます。
本件は、この1項5号に含まれる「性格の不一致」に該当するかどうかが争点となったものです。
「性格の不一致」は、離婚原因のひとつとなることはいうまでもありませんが、その内容は、非常に多義的であり、具体的に何をもって、「性格の不一致」と言えるのかがハッキリしません。夫婦関係が「性格の不一致」の故に円満でなくなったのか、円満でなくなったので、「性格」が「不一致」になったのか。
他人同士が婚姻するのですから、性格が一致しないのは当然のようにも思われます。「なんとなく合わない」ということから出発し、いつしか、どうにもならないほどの亀裂が夫婦間に生じるということになります。お互いの心情が関係しますので、ひとたび夫婦関係が不味くなれば、それこそ、箸の上げ下げ、食べ物の噛む音さえ気にくわないことになり、他に、明確な離婚原因が見当たらないときは、「性格の不一致」という表現が使われるように思われます。
5.この夫婦は、私から見てもミスマッチのように思われるし、また、調停では、女性調停委員がいみじくも喝破されたように、「おふたりは合わないわね。」
夫は、歯科医ですから、立派な仕事についていますので、生活費を入れないとかはありません。暴力を振るうこともありません。不貞(不倫)行為があるわけでもありません。しかし、日常生活のすべての面で、「合わない」ようです。では、何故、婚姻をしたのか、ということになります。妻にとっては、相手は、歯科医だからか、夫にとっては、相手がタカラジェンヌだからかということになります。
私は、依頼者である妻に、失礼とは思いながら、「何故、彼と結婚したのですか」と聞きました。妻は、これまで付き合った人と全く異質の人だったから、かえって惹かれた、結婚してもいいかなと思った、ということでした。
夫は、有名人と結婚するということで、極めて豪勢な披露宴を挙げています。いまさら離婚しましたということはなかなかプライドが許さないし、高額の費用もかけています。生活費、婚姻費用なども妻に十分過ぎるほどの額を支払っているといいます。
妻は、実は、お見合いですが、付き合っているとき、婚約時、婚約後の付き合い中にも、「合わない」「違和感がある」と感じていたと言います。しかし、寿退社して、豪勢な披露宴を挙げているし、結婚した以上は、責任もある、親にも迷惑をかけられない、なんとか耐えて努力してみようと決心したとのことです。2年後にやっと妊娠し、女児を出産しました。夫婦生活も相性が悪く最悪だったと言ってます。出産後は、さらに夫婦関係は悪化します。夫は、歯科医の仕事が遅くまであり、夕食は、常に午後10時を過ぎてひとりで摂ります。疲れているということで、子どもの夜泣きをあやしたりする余裕はありません。おしめを取り替えたり、風呂に入れるのも原則として行えません。こうして何から何まで合わない状態となり、「性格の不一致」として離婚の話になったというものです。
妻は、宝塚で厳しい寮生活や上下関係の生活を経験しています。テキパキと物事を処理し、自分の意見もはっきり主張できる人です。反論書面なども期限にきちんと仕上げてきます。
人にそれぞれの性格があり、婚姻したからといって、一致するようになるものではなく、お互いの成育環境や人生観を含む性格や考え方等の違いを尊重しながら、夫婦関係の円満を追及する努力を続けるのが夫婦の在り方なのでしょう。重要なことは、相手を思う心、愛情のように思われます。これが何らかの理由で欠けてしまうと、「性格の不一致」を例として、一気に破綻の方向に進むように思われます。
単に、「合わない」からといって離婚が認められるほど法律は甘くありません。婚姻をした以上、社会的責任もあります。しかし、非や責任があるとしても、現実に破綻状態にある婚姻関係をなお継続させる必要があるのかどうか、いっそ離婚を認めるべきなのではないかという考えもあります。難しい問題です。
この夫婦の、離婚問題は裁判により無事決着が尽きました。しかし、更なる難問がその後も続くこととなります。次号へ続く。
平成28年6月
「実際にあった裁判事件シリーズ」(強制認知事件)
1.婚外(嫡出でない)子として出生した場合、子あるいはその親(子が未成年の場合はその子の法定代理人)は、実父に対して、子であることの確認を求めることができる。これを法的には、認知請求といいます。実父が任意に認知を認める場合もありますが、争った場合は、子は、実父に対し、裁判所に認知を求める訴訟を提起することができます(実際には、家事事件ですので、家裁での調停から始まり、調停での話し合いで、認知を認めれば、それで解決ですし、調停不調となれば、訴訟になるということです。)。訴訟の結果、認知が認められる場合を強制認知といいます。
なお、法律上は、父又は母が認知できると規定されています(民法779条)が、判例は、「母子関係は原則として母の認知を待たず、分娩の事実により当然発生する。」(最高裁昭和37年4月27日判決・民集16巻7号1247頁)としていますので、実母に対する認知請求の例は聞いたことがありません。
2.さて、私も、実父側の代理人として、このような強制認知事件を担当したことがあります。当時、実父とされた依頼者は94歳、請求者は60歳の女性です。この方は婚姻しており、30代の娘がひとりおりました。
強制認知事件ですから、話し合いによる解決はできず、裁判になったということになります。実父側は、最高裁まで争いました。最終的には認知は認められました。
3.一般に、認知を求めるのは、未成年者であり、未成年の子の養育のためという経済的な要請からされる例が圧倒的に多いですから、本件は、異例の事件でした。認知が認められれば、法律上、その父の子となり、相続権も取得できますし、実父に対して、養育費その他の請求ができることとなります。
4.担当した事案は、次のようなものです。
実父とされる依頼者は、会社の社長であり、世間的にも功成り名を遂げた方です。当該女性の年齢からして、養育費が問題になるものではありません。認知が認められれば、相続権が認められることから、真意は、相続人としての権利主張すなわち経済的な問題にあるものと推察されます。確かに、依頼者は、多額の資産を有しています。
調停前に、女性の代理人弁護士から、任意に認知することを求める、という請求がありました。証拠資料として、写真や手紙などがありました。
この年齢になって認知を求める理由は、「実の子であるという真実を明らかにしておきたい」というものでした。自分の娘にも実の祖父が誰であるかをハッキリとさせておきたいということでした。
5.実父は、この請求には、応じられないということで、私にその法的対応を依頼することとなりました。実父の依頼に基づきその旨の回答をしたところ、調停申立てがされました。 しかし、調停でも、実父の気持ちに変更はありませんので、不調となりました。そこで、訴訟が提起されたということになります。訴訟では、当事者本人尋問が行われましたから、ふたりは何年ぶりかで会ったこととなります。
6.訴訟では、この女性は、真実、この実父の子であるかどうか、が争点です。写真や手紙があるといっても、決め手に欠けています。最近では、DNA型鑑定で科学的に白黒を決するということが考えられます。もちろん、裁判は、裁判官の自由心証主義に基づく証拠判断ですから、必ずしもDNA型鑑定が要求されるものではありません。諸般の事情すなわち間接事実の積み重ねにより、当該女性が実父の子であると認めるに足りる証拠があるかどうかということになります。一般的に、接点がひとつもない状況のもとにおいて、認知請求されるなどということはあり得ないものです。
本件でも、実父と女性の母親との性的関係の有無、その女性が出生した時期の実父とその母親との接点や関係、女性出生後の実父との関係、その母親との関係、実父が子であることを前提にした行動を取っているかどうかなどいろいろな間接事実を積み重ねて、裁判官が証拠を経験則に照らして合理的に評価して認定判断することとなります。
裁判官の判断と常識的な一般人の判断との間には、通常、大きな解離はないはずです。経験則に照らして、そのような事実があれば、一応、子であると認められるという判断はできるものと思います。
私にも、実父の子として出生した可能性はあるものと判断できました。実父は、この母親と経済的な話し合いもしており、一定の金銭を支払っているという事実もありました。「手切れ金」なのか、纏まった「養育費」の一括払いなのか、という金額です。さらには、この女性が専門学校に進学するために上京した際には一緒に生活を共にしていたというような事情もありました。
それでも実父は、あくまでも否定しているわけですから、弁護士としての悩みはつきません。弁護士の仕事は、社会正義の実現のほか、依頼者の正当な利益を守ることにあります。裁判で確定したわけでもない段階では、依頼者の意向を最大限尊重するのでなければ弁護士として責務を全うしたとは到底言えません。
当然、子であることの推定を覆す重要な事実はないものか、この母親と同時期に関係をもっていた男性はいなかったかなどいろいろな調査を尽くすこととなりました。この母親は、戦後の混乱期を通じて水商売をしていたものであり、複数の男性との関係もあったとの噂もありました。しかし、それらを現在、確定することはできないものでした。
であれば、DNA型鑑定をするしかないということになりました。密かに女性のDNAを手にできないものかなどについても真剣に検討しました。
しかし、実父は、自己のDNA型鑑定の実施も拒否しました。覆す最大の根拠を完全に拒否したのです。
実父の真意はどこにあるのか、を考えました。あくまでも自分の子であることを否定するのは、「戸籍が汚れる」ことを嫌がったのか、自分の嫡出子達に合わせる顔がないと考えたか、この年になって婚外子がいるということを社会的に知られたくない、等々がありましたが、実父から直接の説明はなく、あくまでも子ではない、というだけです。裁判所も、調停及び裁判手続を通じて、和解による解決を示唆しています。実父は、和解による解決にも応じません。任意に子であることを認めることはしたくない、という考えに揺らぎはないというものでした。
女性の代理人弁護士も当事者の年齢、社会的地位に照らせば、いまさら真実を明らかにすることよりも、金銭的解決の方向もあり得ると考えているように見えます。その場合は、相続権があることを前提とした解決金を支払うことを求めるというものでしたが。
和解になれば、通常考えられる内容は、「女性が実父の子であることを認める。ただし、子は、戸籍上の認知の届をしない(民法781条では、その届をすることにより、戸籍上認知されたこととなる。)。実父は、女性に対し、金○億○○○○万円を支払う。女性は、実父に今後一切経済的な請求をしない。実父の相続人らに対しては、相続権を主張しない。」というものになります。
裁判所は、子であることを否定するのであれば、DNA型鑑定の実施を勧めましたが、実父はこれを断固拒否したことは前記のとおりです。
したがって、和解もできず、判決ということになり、前記のような結末になったということになります。
女性も実際に本当の子であるからでしょうか、実父である依頼者の気持ちも理解できるとして、子であることは裁判上確定しても、戸籍上の届は絶対にしないということを約束してくれました。これも異例なことでした。
7.ところが、すっかり安心していたところ、判決が確定していることから、管轄区役所から届出をしてくださいと女性に催告があったということ、届出をしなければ役所として強制的に戸籍に載せる、ということの連絡がありました。
女性の弁護士と私は、それは本人の意思に合致しない、社会的に混乱をもたらすだけであり、誰も喜ばない、当事者の届をもって初めて籍に入るのであるから、その当事者が任意にはしたくないと言っているのであり、役所が勝手に籍に入れることは断固取り止めて欲しいとの申し入れをし、かつ、法務局にも掛け合いました。しかし、判決が出ている以上はやむを得ないこととなり、結果的には戸籍に載ることとなりました。
それから5年後に実父は亡くなりました。
8.女性は実父の戸籍に認知された旨の記載がされましたから、相続人として遺産分割協議に入ることとなりました。大変な混乱が起きるかと心配していましたが、救いは、この女性の存在が他の相続人も薄々気がついていたということです。前記のように一時引き取った時期があり、一緒に生活をしたこともあったということから、父親の子であるというなら、それもあり得るということをスムーズに受け容れられました。嘘のような本当の話でした。実父の偉大さがひしひしと感じられたことでした。
9.平成24年5月に遺産分割協議が成立しました。この時点では、民法900条4号ただし書があり、婚外子は、認知されても、嫡出子の相続分の2分の1と規定されています。
しかし、法律家の間では、この規定が見直されることは必至という理解でした。既に高裁段階では、違憲の判断が出ており、最高裁に上告されていることから、いずれ違憲の判断が出る可能性が大であるというものでした。違憲判決が出れば、遺産分割協議に影響が出ることは明らかです。最高裁の判断が出る前に解決できたのは女性の代理人弁護士の協力もあったからと言えます。
10.最高裁判所大法廷平成25年9月4日決定(判例時報2197号10頁)は、民法900条4号ただし書の規定を違憲無効とし、非嫡出子の相続権は、嫡出子と平等であり、同相続分を取得できると判示しました。
これを踏まえて、民法900条4号ただし書は削除されていますので、現在は、認知された非嫡出子の相続分も嫡出子と同等であるとして取り扱われるようになりました。そして、同決定は、同決定で違憲無効とされたこの規定が有効であるとしてされた遺産分割には、影響を及ぼさないとも判示していることから、女性を含めた遺産分割協議は、この最高裁決定の前にされているため、有効として確定することとなりました。
11.なお、女性は、実父の長女とは年齢も近いためか、非常に似ていることを念のため追記しておきます。
平成28年5月
「実際にあった裁判事件シリーズ」(不倫行為を理由とする損害賠償額の算定考慮事情について)
1.本号では、不倫行為を理由とする損害賠償額の算定考慮事情について、取り上げたいと思います。
本例で言えば、妻からの損害賠償請求訴訟において、不倫相手の女性が婚姻関係破綻の抗弁という主張をしてもそれが奏効しなかった場合、裁判所は、不倫女性に対し、一定の損害賠償支払を命じます。
2.この種の事案では、一体、どれくらいの金額の損害賠償を命じられるのでしょうか。また、その場合の算定上考慮される事情はどういうものがあるのでしょうか。
大方の興味を惹くところもあるかと思い、取り上げることとしました。
3.過去の裁判例について検討してみますと、およそ次のような事情が考慮されていると言えます。
当事者の年齢、性別、婚姻期間、婚姻生活の状況、原告(不倫されてしまった者)の落ち度、被告(不倫した者)の認識・意図、不倫期間、不倫の具体的内容・頻度、不倫の主導者は誰か、妊娠(出産)の有無、夫婦間の子どもの有無、夫婦の子どもへの影響、被告から原告に対する慰謝のための措置の有無・程度、被告の反省謝罪の有無、といった事情が考慮されると整理することができます。
事件は、どんなものでも全く同じものはありませんので、微妙に異なる個別の事情に応じて、諸事情のうち特に考慮される事情は自ら異なってきます。
4.手元の裁判例を整理すると、損害賠償額は、およそ次のようになります。もっとも事案が異なればこの金額が増減されますので、金額のみを一人歩きさせることは危険ではあります。あくまでも参考程度にご理解ください。
以下は、平成14年以降に裁判例の中の本件事案のように妻から不倫女性に対するケースを取り上げてみました。
①岡山地裁判決平成14年7月19日(120万円)
②岡山地裁判決平成15年6月10日(200万円)
③岡山地裁判決同年9月26日(200万円)
④岡山地裁判決平成16年1月16日(250万円)
⑤岡山地裁判決平成17年1月21日(250万円)
⑥岡山地裁判決平成18年4月25日(300万円)
⑦岡山地裁判決平成18年10月19日(300万円)
⑧広島高裁岡山支部判決平成19年9月27日(300万円)
⑨岡山地裁判決平成19年10月5日(140万円)
5.不倫行為に基づく損害賠償請求訴訟は、夫(妻に不倫された)から男性(妻と不倫した)に対する請求事案もあるわけですから、不倫行為一般論として捉えたときに、どれくらいの損害額が認容さていれるかということも考えて見なければなりません。しかも、この種訴訟は昔から存在しますので、どれくらい遡って検証するかという問題にもよりますが、貨幣価値の違いがありますから、あまりにも昔のことを取り上げても金額としては参考にならないと考えることもできます。
最近でも、50万円という認容判決も見たことがありますし、100万円以下というケースは珍しくありません。50万円程度の賠償額を認めるくらいなら、慰謝料は発生しないのではないかという見方をする人もいるかも知れませんが、不倫行為が認められ、婚姻関係が破綻していると認められないときは、やはり一定の金額の慰謝料は認容されるということを意味しています。また、そもそも日本の裁判所の慰謝料に対する考えが極めて低いということも反映しているということができると思います。
6.最近の統計的な検証によりますと、平均額216万円、最高額は600万円となります。
皆さんも時々、ネットなどで紹介されている「相場」を参照することがあるでしょう。不倫の場合のネット上の「相場」は、100万円から300万円とか、200万円から300万円などと表示されていると思います。
実務的には、200万円あたりに基準をおいて、事案に応じて、増減させているものと考えられます。
7.このような相場を前提としますと、不倫行為をした者は、200万円前後の賠償を覚悟しなければならないということになるわけであり、また、請求する側は、おおよそ200万円あたりを基準にしたうえ事案の特性に鑑みて、300万円を要求したりする、ということになるのだろうと思います。
もっとも、現実には、裁判で請求する側は、訴状には、300万円程度ではなく、1000万円などと請求する例が多いものです。
8.本例に照らして、各考慮要素について見てみましょう。
ア 原告の年齢が若ければ、今後の人生において、被告によって精神的苦痛を被ったという事実を抱えて生きていくことになりますので、精神的苦痛が増大すると言えます。本
例の原告(妻)は40歳でした。
イ 原告の妻とその夫は、約15年という長期間にわたって婚姻関係を継続しており、平穏な関係を築いていたため、被告(不倫女性)による婚姻共同生活の平和に対する侵害は
大きいものがありました。
ウ 原告と夫との婚姻関係はそれまでは良好であったため、夫と女性が不倫に及んだことについて、原告に落ち度はありませんでした。
エ 被告は、原告の夫との不倫関係を主導した面があります。自分のホテルの部屋に引き込んでおり、かつ、妊娠しています。女性は医師ですから、妊娠を避けることは当然で
きたはずのものです。妊娠もしたということは、原告の婚姻関係を積極的に破壊する意図があり、これによる婚姻共同生活の平和への侵害及び原告に対する精神的苦痛は
甚大でした。
オ 不倫の期間については、極端に短い場合のみ慰謝料の減額事由として考慮されますが、被告による不貞行為は、平成26年6月14日から始まり長期間にわたっている上、
被告は、今後も継続すると明言しており、原告に対する精神的苦痛を増大させるものと言えます。
カ 被告は、原告の夫と新居を探し、同居を始め同棲を始めました。これも婚姻共同生活の平和への侵害及び原告に対する精神的苦痛を増大させるものです。
キ 被告は、不倫になることを否認しており、原告に対して一切謝罪することもないため、原告に生じた損害の事後的回復は全くなされていないことも大きな増額事由となります。
9.不倫行為が継続している場合、このような公序良俗に反する関係を解消させるためには、法的手段としてとり得るものとしては、高額な損害賠償請求を認容することでしか解決できないように思われます。損害賠償責任が一種の制裁として機能することが期待されると考えます。
ただ、この種の事案では、不倫女性が賠償額を支払うというより、自らは負担せず、実際にはこの夫に支払わせることとなる例が多いとも言われています。本来、妻は、女性からしっかりと賠償額を取ろうとするのですが、現実には、なかなかそのようにはいかない場合もあるということです。不倫女性が全く痛痒を感じないというのでは、正義は貫かれませんね。
平成28年4月
「実際にあった裁判事件シリーズ」(不倫行為損害賠償請求事件の続き)
1.前号では、不倫相手の女性が婚姻関係破綻の抗弁という主張をして損害賠償支払義務を争ってきた例を取り上げました。
不倫が発覚し、損害賠償を請求された場合、争うときは、この抗弁の主張をするのが通例であるといってよいかと思います。
類型としては
A 本例のように、妻から、女性に対する慰謝料等請求
B 夫から、妻と不倫をした男性に対する慰謝料等請求
C 上記A及びBの類型に子どもが加わる例もあります。
また、妻、夫と書きましたが、提訴時には夫婦は離婚している場合もありますので、上記の例で、元妻、元夫という場合もあります。
不倫が理由で、夫婦の婚姻関係が破綻したということで、離婚の原因を作った不倫相手に損害賠償(慰謝料等)を請求する事案があります。
2.いずれの場合でも、実際は、潔く、非を認める例に当たったことはありませんし、仮に、女性の代理人になったとしても、妻と夫との婚姻関係は「本当はうまくいっていなかったのだ」というようなことを依頼者たる女性から聞けば、この婚姻破綻の抗弁を主張しなければ弁護士としては、依頼者の正当な利益を守ったとは評価されないでしょう。
おそらくその気になれば、どんなに良好にみえる夫婦の間にでも、婚姻関係がうまくいっていない形跡を探すことはできるものです。夫婦として生活をしていれば当然のことでしょう。また、子どもの教育を巡っての意見の違いもあるでしょうし、相手に対する愛情や期待から、仲の良い夫婦でもひとつやふたつ言い争いはあるでしょう。むしろ、愛情がある普通の夫婦だからこそ大きな声で怒鳴ることもあるかも知れない。暫く口も利かない時期があるからといって、離婚に至るようなものではなく、いつの間にか、元の状態に戻っているというのが多いかと思われます。夫婦喧嘩は、時として夫婦関係を堅固にすることもあるでしょう。仲直りの切っ掛けが掴めずにダラダラと悪い関係が続くこともあるかも知れないが、これはできるだけ早く解消しておきたい。
実は、本例でも、女性側に指摘される事実関係がないわけではなかった。
3.本例では、Y男がZ女と不倫関係を結んだ6月14日(X女は、当然このような関係があることを知らない。)から1か月ほどした時期に、小6の娘の学校の問題があり、電話での遣り取りではあったが、娘の中学進学を巡る教育方針を巡って言い争いが起きた。Z女側は、これを夫婦喧嘩であり、離婚状態すなわち婚姻関係の破綻、夫婦関係が悪いことを示す事象のひとつであるとする。
Y男は医師としての業務は救急であるため、ほとんど帰宅せず、病院に泊まり込むことも多く、また、帰宅するとしても時間が遅かったりしていた。X女も医師であるため、夫であるY男の事情は良く理解できる。電話も勤務先にしたものであった。しかし、3人の子育てもほぼ任せっぱなしの状態であり、X女自身、自らの実績も上げたいという意欲があるのであるから、娘の教育方針を巡ってかなり激しいやりとりをした。話の流れで、「離婚」の言葉も出た。
それから2週間後、Y男は、久しぶりに帰宅し、「持ってきたから」と言ったきり,自室に閉じこもった。X女がY男の机の上に置かれた離婚届に気づいた。離婚届には、Y男が記載すべき事項欄には、すべて書き込みがあり、後はX女が記載すべき事項に書き入れるばかりになっていた。
X女は、一体何を考えているのだろう、何も話さないY男と話をしてみたい、特に6月中旬ころから、なんとなくよそよそしいし、更に帰宅することが少なくなったこと、夫婦としての会話がなくなったことに強い違和感を抱いていた。そのために、妻として記載すべき事項欄に書き込み、さらに、署名をしたが、押印はせずにそのまま自分の机の上に置いておいた。この離婚届に必要事項を自ら記載して署名までしたことをもって、夫婦関係は破綻していたとZ女側は主張している。
4.このような経緯で、離婚届に署名等をしたことをもって夫婦関係は破綻していると見られるかどうかが争点となった。
裁判離婚が認められるためには、夫婦関係が破綻していることが必要です。長期間の別居だとか、夫婦関係がないとか、いろいろな事実関係から破綻を推認することとなりますが、さて、本例のように離婚届に押印はしなかったが、署名等はしたという場合、これは夫婦関係の破綻を意味するものかどうか。
破綻が認められれば、X女からの損害賠償請求は棄却されることになろう。離婚事件での婚姻関係(夫婦関係)の破綻の意義と不倫関係の場合の婚姻関係の破綻の意義とは同じなのかどうかという問題もあります。
以下次号
平成28年3月
「不倫行為損害賠償請求事件」
1.本号は、妻から夫と不倫行為をした女性に対する損害賠償請求の事案である。
不倫であるが故にその恋愛には刺激があり、世間的には許されない関係だから、回りが必至でやめさせようとする。そうすればするほど当事者は燃え上がる、という非常にやっかいな事案である。
反対を押し切って、不倫相手と結婚すれば、それは日常になり、こんなはずではなかったと、急に熱が冷め、離婚に至る例も多数ある。
だからと言って、依頼者にその例を説明したうえで、「余り騒がない方がいいですよ」などとアドバイスをしてもほとんど効き目はないのが実際である。
2.日本の法律では、婚姻関係は、法的に保護されている。したがって、この平穏な婚姻共同関係を破壊しようとする者がいれば、一定の法的制裁がある。損害賠償がその例である。
だから、世間的には、不倫はやってはいけないもののひとつとして肝に銘じているところである。大方の自制心は、ここから来ている。誰も平穏な婚姻関係を壊してまでは、という思いと世間の目がある。
3.X女(40歳)は、Y男(42歳)と婚姻し、既に15年が経過している。ふたりの間には、3人の未成年の子どもがいる。Z女(42歳)は、Y男と職場の同僚であり、Y男とともに医師である。X女とY男との間は、特に目立った夫婦間の亀裂はない。X女は、Y男と離婚する気持ちはない。Z女との関係が発覚した後も同様である。
Y男とZ女とは、提訴1年前に、海外の学会に出張した際に、男と女の関係ができてしまった。職場の同僚であるが故に、Z女は、Y男がX女と婚姻していること、すなわち妻がいること、そして3人の子どももいることを知っていた。
したがって、Z女は、X女という妻がいることは知っていたのであるから、Y男との肉体関係を結ぶことは明白な不倫関係になり、これを認識していたということになる。その後、Y男とZ女との関係は急速に発展し、3か月後には、Y男は、X女ら家族のもとから出奔し、Z女と同棲するようになり、現在に至っている。また、結局は流産したが、Z女は、Y男の子を一度妊娠している。
このような事情のもと、X女は、Z女に対し、慰謝料1,000万円の損害賠償を請求する訴訟を提起した。
慰謝料額については、最終的には裁判所が判断する事項であり、その額を争うことは想定されるところ、このような明白な不倫であるにも関わらず、Z女は、損害賠償支払義務を全面的に争う姿勢を示した。
4.婚姻関係破綻の抗弁という主張
この種の事案では、Z女が妻であるX女からの損害賠償請求を免れる方法は、X女とY男との間の婚姻関係は、Y男とZ女が肉体関係を結んだ時点で、既に破綻していたことを主張しこれ証明した場合である(婚姻関係破綻の抗弁というものである。)。
一般的には、なかなか破綻を証明することは難しいが、既に、長期間別居していたり、そのために妻も離婚してもいいと考えている夫婦もあるから、あり得ないことではない。Z女もこの抗弁を躊躇なく主張してきたのである。
平穏な婚姻共同関係を保護するための法理論であるから、形式的には夫婦であっても、実態は、婚姻関係が破綻していて形骸化しているならば、保護に値しないとして、損害賠償支払請求を認めないのも裁判例の採用する見解だからである。
以下次号に続く。
平成28年2月
「実際にあった裁判事件」
1.本号で取り上げるのは、ある地方の小さな町で,実際に起きた裁判事件についてである。示唆を与えるのは、戦いの在り方である。なんでもかんでも争えばよいというものではない。
宗教法人Aは、檀家をおよそ300戸を擁するお寺を経営している。このお寺は、400年も続いている由緒あるものである。しかし、その代表役員(住職)Bは、50歳になったばかりであるが、若いころからの放蕩的生活や真面目に宗教活動を行わず、お経を上げるにしても、まずはお金を払えという態度であるため、年配の檀家からは顰蹙を買っている。檀家と寺との関係には一触即発的なところがある。
お寺は、30年ぶりに、庫裡改築の要があるとして、檀家各戸に対し、1戸当たり金30万円の寄進とその他に特別寄進を募ることとなった。住職Bは、改築資金として見積もったところ、およそ1億2000万円が必要だとしている。寺は、自己資金として2000万円を金融機関から借り入れるなどして拠出する用意があるが、それ以外に資金はないので、檀家で負担してほしいというものである。
2.檀家300戸のうち、3分の2に当たる200戸ほどは、1戸当たり30万円もの寄進は極めて難しいし、檀家が負担すべきものがあるとしても、そのような高額(1億円)な建築費用は必要なのかと、疑問を持つ者が多く出た。寺が開いた説明会では、賛同するどころか、反対意見や計画の見直しを求める声が圧倒的に大きかった。そこで、檀家の中心人物が音頭を取り、適正な改築になるための検討をすべきだという主張のもとに、200戸から成る檀家会が結成された。檀家会は、敷地面積30坪程度で、平屋建てのものにするならば、4500万円程度で改築できるという独自の改築計画案を作成し、寺に提案した。
しかし、寺は、これを受け容れず、双方は平行線を辿ることとなって、数か月が緊張した状態のまま経過した。
檀家会の試算によれば、寺が自己資金として2000万円も出せば、残りの2500万円を檀家が全体として負担すれば足りることとなるので、1戸当たり8万円程度で済む勘定になるというものであり、檀家会の計画案は大方の賛同を得ることとなった。
3.問題を一層混迷にしたのは、檀家会が、寺の毎年の年収は少なくとも2000万円もあることを実証したからである。檀家はほとんどが同じ町内に住むので、どこそこで、葬儀や法事があったことは、檀家会のメンバーがその気になれば、かなりの確度で調べられるのであり、そのため寺の収益を計算できる状況にあった。寺は、これを否定したので、檀家会は、寺の経理状況を明らかにするよう迫ることとなった。檀家会には、その主張を裏付ける確信のようなものがあった。住職Bの性格からして、寺の資金は一切使おうとしないだろうとの確信があったことによる。
寺が経理内容を明らかにしないので、檀家会は、寺に対し、宗教法人法25条2項及び3項に基づき、寺に備え付けられている寺の規則等、役員名簿、財産目録、収支計算書、貸借対照表等の書類及び帳簿の閲覧請求を求めることとした。この法によれば、寺は、信者からの請求に対し、それに正当な利益があり、また、不当な目的によるものでない限り、その閲覧請求には応じなければならないというものである。
4.ところが、寺は、この閲覧請求は、不当な目的によるものであるとして、一切、応じない旨回答してきた。
そのため、檀家会のうち25名が代表となって原告団を結成し、平成26年5月、裁判所に対し、書類及び帳簿の閲覧請求訴訟を提起した。その数回にわたる裁判期日を経て、平成27年11月16日に裁判所において和解が成立し、この裁判は、解決した。
原告団の中には、あくまでも判決を志向した者もいた。和解というのは、寺と仲直りしたような感じがするので、心情的に受け容れ難いというのが主たる理由である。しかし、原告団及び檀家会は、最終的には、裁判所が勧める和解案に従い、和解による解決を受け容れた。
和解による解決を受け容れたのは、判決では、勝訴したとしても書類及び帳簿の閲覧することしか認められないのであり、閲覧とは、謄写を含まないから、ただ見るだけで終わってしまうからである。原告団を構成する檀家会としては、寺には、今後の運営について、宗教法人法や寺の規則等に基づく、適正な、正しい運営をして貰いたいと考えている。むしろ、主たる目的は閲覧よりもここにあったと言って良い。そのためには、手元に是非とも寺の規則等を持っていることが必要なのである。
裁判所の和解案は、規則等のコピーを寺から原告団に交付するという条項になっている。和解であるから、一部、寺に譲ったところもある。それでも、原告団は、判決では得られないものを獲得することができたことになる。
5.寺は、信者たる檀家からの閲覧請求に対して拒絶したため、このような裁判の提起を受けるに至り、また、裁判でも戦ったために、最終的には、裁判所案による和解を受け容れざるを得なくなったものである。結局、寺は、失うものの方が多かったと言わざるを得ない。地方紙には、裁判提起時からその顛末が報じられ、また、和解内容も報じられた。
寺は、戦略を誤ったものと言わざるを得ない。宗教法人法25条の法意は、寺に備え付けられている書類及び帳簿の閲覧を認めるだけである。寺が、意地を張らず、裁判提起前に檀家会に寺が備え付けている規則等の書類や帳簿を閲覧させるだけに留める戦略を採っていたならば、檀家会がここまで結束を固められず、また、世間の関心も集めることなく、単に、寺の備え付けている書類等の閲覧で静かに終わっていたものと考えられる。
檀家会は、今後、この和解調書に基づき、次々と寺に対し、その正しい運営を求めて圧力をかけていくことになることはほぼ間違いがない。
以上
平成28年1月
「パワハラの防止対策例その2」
1.前号では、パワハラとは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」であり、具体的な言動例としては、「暴行(傷害)、暴言、脅迫、名誉毀損、侮辱、隔離、仲間外し、無視、仕事の妨害、明らかに不要なあるいは困難な業務の強制(過大要求)、明らかに程度の低い仕事の強制や仕事を与えないこと(過少な要求)、私的なことに過度に介入すること(個の侵害)」等が典型例として当たることを説明した。
要は、適切な指導、注意、叱責であれば、部下を発憤させることに役立つであろうが、その言い方や指摘の状況によっては、名誉を毀損したり、精神的に追い込んでしまうことがあることに注意しなければならないということである。
「何を言ったか」よりも「どのように言ったか」が重要であると言われる所以である。
2.セクハラと異なり、パワハラの判断は極めて難しく、業務の遂行過程における言動が、業務の適正な範囲を超えているかが問題とされるのであるから、パワハラをしたと指弾される上司側にも十分な言い分がある可能性があることも前号で述べたとおりである。したがって、会社としても、この上司のパワハラに対し、どのように対処するのが適切なのかに悩むことも多い。弁解の余地がないと思われる暴行、傷害の場合ですら、上司には言い分があるかもしれない。
もっとも、このような暴行、傷害行為自体は、社会通念上許されるものではないであろうから、会社としては、この上司に対して、就業規則上の処分を検討することとなるのはやむを得ない。要は、どのような処分が行為とバランスが取れた適正な処分といえるかということになる。部下も会社がどのような処分を上司に対して行うかに関心をもってみている場合が多い。しかし、処分は、あくまでも会社としての立場で行うものであり、部下が被害者であるとしても、部下に処分請求権のようなものがある訳ではない。
部下の被害感情は、処分を決定する際の情状として斟酌をすることができるが、被害者のために処分するものではないことには注意を要する。
処分の内容を被害者に教えたりする場合があるが、プライバシーの問題と関わるので、この取扱は十分に配慮することが必要となる。
3.さて、職場内で起きたことであるから、部下から上司に対して、直接抗議したりすることは一般的には困難であると思われる。そのため、部下は、法律事務所に相談に行き、弁護士から上司に対して、損害賠償を請求する書面を郵送することとなる。しかも、この内容は、初めての人が手にすれば、強い脅しのように感じるものである。すなわち、一定期限までに誠意ある回答(賠償金の支払い)がない場合は、提訴及び刑事告訴も辞さないという内容の内容証明郵便だからである。そして、請求する賠償額は、考えたこともないような高額だと受け止められる場合が多い。上司が簡単には払えないような金額なのである。高額になっているのは、制裁の意味を込めているからであり、また、反撃のつもりなのかもしれない。上司にとっては、そのような事態が起きたことは否定しないまでも、双方納得のうえで、その場では、解決したつもりでいることから、いきなりの請求に思われ、書面の内容を読んでさらに驚愕することとなるのである。
4.上司がこのままこれを放置した場合はどうなるのか。会社は、上司からこのような状況を説明された際に、取るべき対応はどういうものなのか。
上司が放置すれば、提訴及び刑事告訴がされるおそれは十分にある。そのつもりでの弁護士委任だからである。では放置しないで、相手の弁護士に連絡するとする。謝罪を要求され、高額な賠償金についての交渉となるが、適切に行えるかが問題となる。おそらく電話を入れて相手の懐を探っても、譲歩案を引き出すことは難しいと思われる。
そこで、会社に相談することとなろう。
会社としては、上司を庇えるのかどうかを判断するだろうし、庇えないとしても、その高額な賠償金はなんとかならないだろうかと考えるであろう。また、そもそも、職場内でパワハラ事象が起きたことに安全配慮義務の観点から会社にも落ち度があるのではないかと考えることもあるだろう。そうであれば、他人事として放置することはできないこととなる。
理由もなく、会社が立て替える訳にもいかない。かといって、上司には、払える限度がある。一時、会社が不足分を立て替えるということは取り得る方法かもしれない。立て替えるとして、以後、再発のないこと、今まで以上に会社の仕事に精励することを誓わせることとなる。
当該部下が会社をこれを機に辞める場合と辞めない場合とがあるが、これによっても会社としての対応には異なるものがあろう。部下がもはや会社に戻らず退職するという場合は、相手の言い分を呑んで解決することも一法である(といっても法外な金額に応ずる要はないと考えるが)。逆に会社に残るという場合はどうだろうか。相手の一方的な案に応じたということであると上司との間に蟠りが生ずることは否めない。
また、部下にとって、何事も弁護士に委任すれば、自分の言い分が通ってしまうという成功体験もけっしてよいことばかりとはいえないだろう。
いろんなことを考えると、会社の顧問弁護士に入って貰い、法的にかつ常識的にしかも抜本的に一挙に解決することを模索することが良策と考えられる。
弁護士同士の交渉であれば、法的な観点からある程度適正なものになると考えられるからである。
会社が、部下から請求の相手にされている場合は、当然であるが、単に上司に対する請求のみで、会社には請求がない場合でも、会社は、上司の使用者としての責任や、労働環境の安全配慮義務の観点からこの問題を解決することにメリットがあるのであって、会社の顧問弁護士に対し、この上司の問題解決に向けて代理して貰うことに十分な根拠があるものと考えられる。
以上