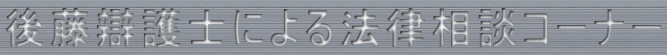
| かけはし誌上コラム(かけはし掲載分) | 羽田鉄工団地協同組合 |
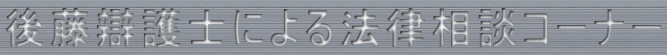
| 最新号(平成29年3月) | |
| 1月 | 「実際にあった裁判事件シリーズ」(名誉毀損事件) |
| 2月 | 「遺言あれこれ その5」 |
| 3月 | 「遺言あれこれ その6」 |
平成29年3月
「遺言あれこれ その6」
1.本号は、「遺言あれこれ」シリーズの6回目になります。自分でこっそりと書ける自筆証書遺言書の作成の仕方、作成上の注意点や法定されているその方式に反した場合の効力を巡っての問題につき、引き続き、取り上げることとしました。
皆様ご自身で、自筆証書遺言書を作成する際のご参考となれば有り難いです。
また、皆様の知人、友人、ご親族の方に適切にアドバイス等する際の参考にして貰えればとも思います。
2.さて、今回も、自筆証書遺言書における「印をおさなければならない」の意義について問題になった事案を取り上げます。
前号は、印章による押印はないが、「花押」が書かれていることについての事案でした。「花押」ではだめであるという判断でした。
今回取り上げるのは、署名の下には押印がないが、全く押印がないわけではなく、2枚からなる遺言書と題する用紙に契印としての押印がある場合は、「印をおさなければならない」を満たしているかどうかが問題となった事案です。
私達は、文章を完成させる場合、署名すれば、その下とか横に押印をするのが原則です。署名はしたが、押印がなければ、ハンコの世界である日本では、何か事情があるのではないかと考えるほどです。それでも遺言書の場合は、「印」ありとなるかどうか。
また、遺言書中の署名の下にも押印がなく、契印もないが、遺言書を入れていた封筒を封印する際の綴じ目に押印がある場合は、「印をおさなければならない」との法定の方式を満たしたことになるかが問題となった事案もあり、これも取り上げることとします。
ここで、おさらいです。
民法960条は、「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」と規定しており、民法968条1項は、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」と規定しています。
何故、このような厳格な規定をしているかといえば、遺言書の真意を確保するためです。遺言書の真意をその死後に直接確認することはできないことから、遺言者の真意に基づいて遺言されたことを判断するのに適した方式を定めておき、これを満たすもののみが遺言として効力を有することとしたものです。
この法定の方式を満たさなければ、その遺言書は無効となるというのが法意です。
また、自書のほか押印を要求する趣旨については「遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし
法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解される。」とされています(最高裁平成元年2月16日判決 民集43・2・45)。
3.前号で取り上げた「花押」が「印」と同様に考えることはできないとした最高裁の判断は、我が国において、印章による押印に代えて「花押」を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難いということにありました。
法律が定める方式を緩和することは、方式要件を定めた法の意義を没却し、無用な紛争を招来するおそれもあります。押印でも指印でもなく、「花押」を書いたというのは何か特別の事情がある場合も考えられます。遺言書を有効としたくないために、敢えて「花押」を書いたと考えられるような場合も想定し得ないわけでもありません。このことは前号で紹介したとおりです。
4.東京地裁判決(判例時報2315号93頁)は、2枚からなる自筆証書遺言書には、日付と、遺言書の署名はあるが、押印がなかったが、しかし、1枚目と2枚目の表面にまたがり遺言者の実印で押捺されていた(契印があった)という遺言書が有効か無効かが問題となった事案において、本件遺言は、自筆証書遺言として有効であると判示しました。
前記のように、最高裁平成元年2月16日判決は、「署名した上その名下に押印する」ということが文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして、これに合致するということにあったと言えます。遺言書でもそうだということになれば、署名の下に(横書きであれば、署名の横に)押印があるのでなければ「印をおさなければならない」の方式を満たしていないと解する余地があることになり、このような押印を欠くのであれば、遺言は無効と考える見解もあり得ることとなります。
ところが、法は、押印をする際に、署名の下に(あるいは横に)しなければならないとまでは定めていません。
遺言の効力を巡っては、できるだけ遺言書の最終意思を尊重しようという配慮、また最終意思を合理的に判断して、できるだけ有効として取り扱おうという配慮があるものと考えられます。
前記東京地裁の判決の前に、次のように最高裁判決がありました。最高裁判決平成6年6月24日(裁判民集172号733頁)は、遺言書本文に遺言者の押印を欠いていても、封筒の綴じ目にされた押印をもって民法所定の押印要件に欠けるところはないと判示しました。
この判旨は、文書の完成を担保するとの趣旨を損なわない限り、押印の位置は、必ずしも署名下であることを要しないとしたものと解されますので、この趣旨に従えば、契印をもって押印があるとされ、遺言は有効であるとされたことも頷けられるものと思います。
平成29年2月
「遺言あれこれ その5」
1.かつて、「遺言あれこれ」という題で、4回にわたって、遺言について取り上げました。特に、自分でこっそりと書ける自筆証書遺言の作成の仕方、作成上の注意点や法定されているその方式に反した場合の効力を巡ってのものでした。
2.遺言書は、遺言者の最終意思が尊重されることになっていますので、作成日付の新しいものが優先します。
作成日付というのは、その遺言書に記載された日付のことです。もし、過去に作成した遺言書を変更したい場合は、新しい日付で、遺言書を書き換えればよいことになります。
公正証書遺言でも同様ですが、いちいち公証役場に出掛けて、公証人に訂正の遺言書の作成を依頼するのは手間暇がかかりますし、第一、面倒くさいものです。また、自分がこっそり公証役場に出掛けることは当然にできることですが、他の者に相談などすることになれば、その内容が予め知られるおそれも出てきます。
そのような意味で、なお、自筆証書遺言の意義は大きいものがあると言えます。
3.さて、今回、取り上げる事例は、自筆証書遺言書に印章による押印はないが、「花押」が書かれていることから、法の定める「印」すなわち「押印」があるものとして、その遺言書を有効とすることができるか、それとも、「花押」は印章による押印ではないので、「押印」がないものとして無効となるか、という点が問題になったケースです。
皆さんは、どう思いますか。遺言者が真実作成したことがはっきりしていれば良いのではないか、また、その最終意思がはっきりすれば良いのではないか、したがって、サイン(署名)があれば、そもそも押印など不要ではないか、その観点から考えれば、「花押」があれば有効だろうとする考え方はあり得るところです。
しかし、民法960条は、「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」と規定しており、民法968条1項は、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」と規定しています。
何故、このような厳格な規定をしているかといえば、遺言書の真意を確保するためです。遺言書の真意をその死後に直接確認することはできないことから、遺言者の真意に基づいて遺言されたことを判断するのに適した方式を定めておき、これを満たすもののみが遺言として効力を有することとしたものです。
この法定の方式を満たさなければ、その遺言書は無効となるというのが法意です。
4.ところが、印章による押印ではない指印による押印について問題となった事例では、最高裁平成元年2月16日判決(民集43・2・45)は、自書のほか押印を要求する趣旨について「遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解される。」としたうえで、押印は、指印をもって足りると判示し、指印による押印をした遺言書を有効としました。
指印は、その概念自体は明確であるうえ、押印と同様に同じ形象が繰り返し再現されるものであり、究極的には個人を特定する機能が高いという実質的理由があります。他方、「花押」は、押印のような再現性はなく、個人を特定する機能も高いとは言えないとみられ、指印と「花押」を同等のものとみることはできないと思われます。このような説明が可能ですから、指印と「花押」を別異に扱っても、そのことに合理的な理由があることになります。
なお、例外的な事例として、約1年9か月前に帰化した白系ロシア人が英文の自筆証書遺言を作成し、署名はしたが、押印がなかったという遺言書について、最高裁昭和49年12月24日判決(民集28・10・2152)は、「主としてロシア語又は英語を使用し、日本語は片言を話すにすぎず、交際相手は少数の日本人を除いて、ヨーロッパ人に限られ、日常の生活もまたヨーロッパの様式に従い、印章を使用するのは官庁に提出する書類等特に先方から押印を要求されるものに限られていた等の事情があるときは、遺言書は有効である。」と判示し、押印がない遺言書を有効と判示した例があります。
5.たいがい、遺言をした父親の死亡後に、子ども同士が父親の自筆証書遺言の効力を巡って争うことが多いものです。
本事例もその例です。長男から次男に対して、父親所有であった土地が自筆証書遺言により、長男が取得したとして、次男に対し、その土地についての所有権移転登記手続を請求したというものです。
次男の主張は、自筆証書遺言には、「花押」はあるが、「押印」がないから、無効であるというものです。これに対して、長男は、「花押」があるとして遺言の有効を主張しました。
「花押とは、署名の下に書く判。書判ともいい、中世には、判・判形とも称した。初めは名を楷書体で自署したが、次第に草書体で書いた草名となり、さらに様式化したものが花押である。」とされています(広辞苑6版)。
世の中には、氏名の下に片仮名を崩したサイン様のものや、ひらがな1文字を○で囲って押印がわりをさせている例があります。このような書き方についても、自筆証書遺言の「印」にあたると言えるかが問題となった先例があります。裁判例はこれを否定しています(東京地判平成25年10月24日 判例時報2215・118)。
6.今回、取り上げた「花押」の事例では、最高裁は、「押印」があるとは認めず、遺言書の効力を否定しました(平成28年6月3日判決 判例時報2311・13)。その理由は、我が国において、印章による押印に代えて「花押」を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難いということにあります。
法律が定める方式を緩和することは、方式要件を定めた法の意義を没却し、無用な紛争を招来するおそれもあります。押印でも指印でもなく、「花押」を書いたというのは何か特別の事情がある場合も考えられます。遺言書を有効としたくないために、敢えて「花押」を書いたと考えられるような場合も想定し得ないわけでもありません。例えば、ある特定の相続人から責められて、やむなくその者に有利な内容の遺言書を書かざるを得なくなったが、他の相続人のことを考えると、不本意なので、敢えて、無効となるように、方式要件を満たさない遺言書を作成する場合もあると考えられるからです。世の中は、まさにいろんなしがらみの中にあります。遺言者が無効となることを承知で遺言書を作成する場合もあるなどとは善人にはおよそ考えも及ばないことかも知れませんが、現実の世間にはないわけではないということです。
7.「争族」を避けるために、できるだけ遺言書を作成しておきましょう、とは良く言われることです。自筆証書遺言による遺言の意義も前記のとおり大きいものですから、法律が 定める方式要件をしっかりと遵守することで、無用な紛争を避けつつ、遺言者自身の真意を反映させることとしたいと思います。
以上
平成29年1月
「実際にあった裁判事件シリーズ」(名誉毀損事件)
1.平成28年12月22日、東京高裁は、新聞記事に対して問い合わせてきた男性の読者に対し、新聞社の担当者が、男性がやや乱暴な語調で自分の主張を繰り返したことにこらえきれず、「ちょっと頭おかしいんじゃないですか。」などと発言したことは、侮辱的な発言で不法行為に当たるとして、慰謝料1万円と弁護士費用相当損害金1000円の合計1万1000円の損害賠償請求を認容しました。
原告は、50万円の損害賠償請求をしたとのことですから、裁判所の精神的苦痛に対する慰謝料を評価する際の基準がかなり低いということが、この例からも十分に窺われます。おそらく1万円の慰謝料が欲しくて弁護士に依頼してまで裁判したというより、侮辱的発言を許しがたいと考えたからに違いないと思われます。
名誉毀損は、人の名誉という人格権に対する侵害ですから、金額もさることながら、名誉の回復が主であり、相手に慰謝料を払わせることによって謝罪させることができたというところに大きな意味があるように思われます。したがって、金額は二の次となり、名誉毀損が認められるかどうかに重点が置かれるようになります。
そもそも、日本では、人に精神的苦痛を与えた際に命じられる慰謝料額は、アメリカなどに比べると著しく、低額であることはご承知のところと思います。その中でも特に、顕著なのは、名誉毀損事件における慰謝料額ということになります。
不倫相手に対する慰謝料額については、以前に紹介しましたが、本号では、名誉毀損事件における慰謝料額について取り上げてみたいと思います。
なお、平成28年12月17日までに、東京地裁は、イオンが文藝春秋に対して、その発行にかかる週刊文春の記事である「『中国猛毒米』偽装」「イオンの大罪を暴く」において名誉を毀損されたとして訴えた事件において、約2490万円の損害賠償請求を認容しました。これはかなりの高額ですが、イオンが意見広告を載せた費用なども損害と見積もったことから金額が大きくなったようで、特殊な例かと思われます。
2.名誉毀損事件についての論点はいくつかありますが、本号では、匿名記事についての名誉毀損の成否と、刑事事件で有罪判決が確定した者についても名誉毀損が成立するのかなどについて取り上げてみたいと思います。
(1)そもそも、名誉とは何を指すのか。判例では、次のように説明されています。
名誉とは、「人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価」であるとされます(最判平成9年9月9日民集51巻8号3804頁)。
(2)したがって、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるような表現をした場合は、その人の名誉を毀損したこととなり、民法709条により不法行為として損害賠償責任を負うこととなり、同法710条により精神的苦痛に対する損害である慰謝料の支払義務と同法723条により名誉を回復するのに適当な処分である謝罪広告などを命じられることとなります。
(3)匿名(仮名。以下、本号では、仮名の場合も匿名といいます。)による名誉毀損の成否について
本事例では、被告である出版社と著者は、ある単行本において、原告の実名とは異なる「杉岡」と匿名表記にして記事にしました。匿名であるから、原告の名誉を毀損していないという主張をしています。匿名である以上、誰か分からないではないかということです。
しかし、匿名記事でも、記事全体から、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準にした場合に、対象者を特定できる場合は、名誉毀損が成立するということは判例・通説といってよいです。匿名でも対象者を特定できる場合とは、①普通の人であれば特定が可能である場合、②ある程度の知識を前提にすれば特定が可能である場合、③限定された範囲の人にとっては特定が可能である場合の3つの場合がありますが、いずれの場合も名誉毀損が成立し、対象者を特定できる人がどれ位の範囲に広がっているかは慰謝料の額等で考慮される、とされるに過ぎません。
したがって、人の名誉を毀損しないためには、実名を出さないということだけでは足りないことになります。名誉毀損に当たらないようにと配慮したつもりで、匿名にした場合でも、前記のように特定されるような記事内容であれば、名誉毀損が成立し、一定の慰謝料を払わざるを得ないこととなります。しかも、近隣の限られた範囲の人にしか分からないような書き方をしたとしても、上記③の要件が認められるような場合は、名誉毀損が成立しますので、人の名誉を毀損しない書き方をするためには十分に注意をする必要があります。
(4)当該原告は、実は、刑事事件で、有罪判決を受け、確定した人でありました。自らは冤罪であると主張していますが、裁判所からは有罪判決を受けて受刑しています。そのような元被告人についても、名誉毀損が成立するのか、ですが、確定判決をそのまま紹介するような場合は、内容が真実であることが立証できますから原則として名誉毀損にはなりません。しかし、確定判決を忠実に紹介するのではなく、おもしろおかしく事実でないことを織り交ぜて表記をした場合は、名誉毀損が成立する場合があります。本事例もそのような例であり、原告に関わる私的行状を含む事実でないことをあたかも真実であるかのように装い(すなわち客観的にはそれが真実であることを立証できないのに)、おもしろおかしく記事にして、原告の社会的評価を低下させる行為を行ったものです。
人には誰にでも人格権が保障されており、たとえ有罪判決確定者であっても同様です。名誉を毀損するとは、その人の人格及び人権を尊重せず、過度に、その品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会的評価を低下せしめるような記載をすることを指すものですから、全くその犯罪事件とは関係のない私的行状等を殊更に取り上げてさも真実であるかのように装って表記したような場合は、その人の人格権を侵害したことになります。したがって、名誉を毀損するというほかはありません。罪を犯した者であるから、ある程度のことを書かれても受忍すべきであるなどということはありません。ひとたび、罪を犯せば、何を書かれても、文句は言えないのだ、ということにはならないのです。
3.依頼者たるこの原告にも、ある大手の出版社と著者に対して名誉毀損を理由として、慰謝料120万円と弁護士費用相当額12万円の合計132万円の損害賠償を支払うよう命ずる判決がされ、この判決は、そのまま確定しています。
人には、誰にでも人格権が保障されております。いかに表現の自由が保障されているからといっても、他人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるような表現行為は、許されないのだということになります。
以上